小説『Sum a Summer =総計の夏=』(2/5)
第二章 『7月2日(水)』
心臓が痛い。
といっても、別に悪い病気にかかったとか、昨日の寿司ネタが傷んでいたとか、古い雑誌やマンガの魔力で夜を無為に過ごしてしまったとか、そういうことではない。極度の緊張が原因だ。
恐るべきことに、大矢高校ではテストの翌日朝一番から期末テストの成績発表を行うのだ。
初日や二日目のテストなら、まだ採点の時間はそれなりに確保できるのかもしれない。しかし、一学年300人近くいることを考えると、神の業としか思えない。身体をサイボーグ化した教師がいるらしいとか、地下に大量のコビトさんが待機しているとかいう噂もあるようだ。何故か、そのあたりのカラクリを生徒は誰一人知らないため学園の七不思議の一つとなっている。
といっても、実名を発表されるのは各科目の上位10名までだ。名前が載るならひたすら名誉だし、載らなかったとしてもビリなのか11位なのかは本人のみぞ知ることで、やはり緊張は無用とは頭では分かっているのだが。
英語は答案を回収された時点で惨憺たる有様だった。なので、はじめから期待していない。倫理と現代国語はまずまずの手ごたえだったので、それだけが数少ない希望の光だ。
学校に着くと、屋外掲示板には早くも人だかりができていた。
思えば、高校の合格発表もここで大喜びしてたもんだなぁ。つい昨日のことのようだが、もう3ヶ月も前のできごとだ。
生徒と生徒の間から貼り紙を伺う。これは、英語か。まぁ、これは捨てだからな! と思いつつ、恐る恐る10位のところから上に視線を移していく。
……ない、……ない、……ない、……ない、……ない。
というか、あんな意地の悪い問題ばかりで高得点を取れるこいつら、おかしくないか? きっと、奥地会長みたいな典型的ガリ勉タイプばかりに違いない。
乗りかけた舟だ、残りの5人も見届けてやるか。見上げた僕は息を呑んだ。
織賀美月 100点
……おかしい奴が存外身近にいたようだ。おかげで先程までのドキドキ感は一気に霧散してしまった。
その後、物理・歴史・数学でも一文字違わぬ表示を目の当たりにすることとなった。
最後が国語だ。さすが、カオスの伝道師たる泉西潮成というべきか。最高点が79点であった。すっかり、「織賀美月 100点」に見慣れてきたところだが、国語の美月の点は68点で9位だった。
あの美月にも不得手があるのかと思うと、少し安心したような不思議な気持ちになった。それでも10位以内に入るあたりはさすがなのかもしれない。
残念なことに僕の名前はなかった。どうやら、泉西マジックにみごとにはまったようだ。手ごたえがそれなりにあっただけに微妙なショックを感じる。
肩を落として、教室に向かおうとすると見覚えのある顔と目が合った。
銀縁のメガネのブリッジをくいっと持ち上げて、挨拶をしてくる。
「お、瀬田くん。ご無沙汰ですね」
「福路くん、久し振り」
彼は、福路浩二。科学部に在籍しており、以前ちょっとした相談ごとをきっかけに知り合うことになった。
「福路くん、科学部だったね。化学とかどうだった?」
「全然さ。白衣が泣いているよ」
福路くんは少し大げさに天を仰いで「昼休みにヒトミに慰めてもらおうかな……」と呟いた。
福路くんは中学から付き合っている彼女がいるんだよなぁ。羨ましいことだ。二人揃えば、悲しさ半減嬉しさ倍増だよなぁ。
僕の表情に羨望が浮かんだのを感じ取ったか、福路くんは顔を近づけてくる。
「……ときに瀬田くん。彼女は作らないのかい?」
あまりにストレートな問いかけに、息が詰まった。そりゃ、作れるものなら作りたいけれど、彼女などそう簡単にできるものではない。
「福路くんはどうやって蒼井さんと?」
話題をそらすの半分と、学び半分との気持ちでそう切り返した。
「僕らは都市伝説マニアっていう共通の趣味があったからね」
「都市伝説?」
「そう。『ラフテイカー』とか『中央駅のA3出口脇の壁』とか、『童謡作者の無念』とか、『眠れずの薬』とかね。」
「へ、へぇー……」
うーむ、オーソドックスなカップルかと思っていたが意外だ。
「あとやっぱり、元々幼馴染だったというのが何より大きいかなぁ。気軽に話しかけられるから、接触機会は自然と増える。……でも、やっぱり早いうちにアタックしたのが決め手だろうね」
「そっかぁ」
将棋は、攻めが大好きで『攻撃は最大の防御』と揮毫した扇子を作りたいくらいだが、色恋沙汰は四枚穴熊状態だ。やはり、そこら辺が今後のテーマだと痛感する。
「性急過ぎるのは失敗の元だけど、慎重過ぎるのはもっといけない。先手必勝だね。将棋でも言えることだよね」
先手必勝、という言葉には納得できたのだが、将棋も同じという意見はちょっと気になった。
「福路くん、ちょっとだけ脱線なんだけど、将棋って最近は後手のほうが勝率の方が良くなってきているって知ってる?」
「えっ、そうなの!? 知らない知らない」
自分も最近になって知ったことなのだが、どうもそうらしいのだ。
一般的なイメージで考えると、先に指す方は作戦を自分で選べるし、先に攻撃を仕掛けられる。
ところが、『先に指す』ということは裏を返すと『先に戦略を晒さなければならない』ということでもある。
つまり、後手は先手の作戦を見てそれを迎撃できる最良の布陣をしいてカウンターを狙うことが有効だと言う考え方が近年急速に広がってきているのだ。
福路くんがなにやら難しそうな顔を浮かべていたので、より単純化した例えを即興で考えてみた。
グー、チョキ、パーを公開したまま交互に捨てていき、残った一枚で勝負するというゲームがあるとする。
先手は必ず負ける。
先手がグーを捨てたら、後手はパーを捨てる――というように後手が先手の捨てたものに勝つカードを捨てていく選択をすると最後には後手が勝つカードの組合せにできるからだ。
話し終えて、福路くんが「うんうん、それは確かに分かり易い道理だね」と言ってくれたので、僕もすっかり嬉しくなってしまった。
と、将棋は置いておいて、先手必勝の件は真面目に考えないとだなぁ。テストの成績発表で、美月の知名度は一気に上がったに違いない。倍率は一体どこまで跳ね上がるやら……。競争が狂騒を呼ぶ、今日そうならないとも限らない。って僕は何を言ってるんだ。
いや、僕は良く戦ったよ。大善戦だ。開始後それぞれ15分は耐えられたんだから。
食後の4時間目に数学の丹治延登先生、5時間目に英語の石井英美先生の直列つなぎは反則だ。僕も含めて多くの生徒が屍となった。あの人たちは、プロの催眠術師か不眠症セラピストになった方がいい。
とはいえ、今日の授業は無事終わり、ホームルームが始まっている。そして、泉西先生が無駄に高いテンションで教室をドンびかせている。
恐らく、採点が終わった開放感だろう。……まぁ、我々も昨日はこんなだったんだな。「人の振り見てなんとやら」を身体を張って教えてくれているのだ、と僕はプラスに解釈してあげることにした。
さて、待ちかねた放課後だ。軽音楽部の部長、琴羽野先輩からは「将棋部が落ち着くまでは無理してこなくてもちゃんと籍はあるから。皆にも言っておいてあげるよ」という暖かいお言葉をいただいている。
何か将棋部の存在や実績をアピールできることがないか、考えに考えなければならない。
それにはまず美月と泉西先生に現状を伝えて、一緒に考えてもらうのが最善だろう。一人より、二人。二人より三人だ。
あと、泉西先生にはパソコンが使えないかどうかの相談もしたいところだ。昨日はばたばたしてしまい、結局アクションを何も起こせなかった。
白物家電研究部がウェヴサイトで実績を上げたことを思い出し、ITの力も何かの役に立ちそうだというおぼろげな感触がある。
……しかし、なにぶんどちらもランダムにしか現れないのが悩みの種だ。RPGのキャラクターだったら、さぞかし経験値が高いことだろう。
とりあえず、備品を準備して教室で待つことにする。カバンから詰将棋の本を出して、ひたすらレアキャラの登場を待つ。
しばらくすると、和服姿の泉西先生が現れた。僕は待ってましたとばかりにマシンガントークで泉西先生に畳み掛ける。
「白物家電の研究だあ? ふざけた連中だ。あとでお得な冷蔵庫についてたっぷりと事情聴取してやる!」
「そこですか!」
前言撤回、どうやら頭数が増えてもダメなケースもありそうだ。貴重な人生経験になった。しかし、パソコンについては「大江室長に話しといたる。明日、サーバールームを訪ねてみよ!」と存外にまともな回答をくれた。大方、将棋部名目で借りて何か私用で使う算段でも立てているのではないだろうか。
とりあえず、パソコンの件は一歩前進、したのかな。
大矢高校が誇るトラブル発生機が職員室の方向に消えたのを見届け、カバンから緑茶のペットボトルを取り出す。さっき購買部で買ったものだ。これで一息つこう。
ボトルの脇におまけが貼り付いていた。これは……。最近、ひそかにブームになっている〈クマッタ〉のストラップか。
勉強とか料理とか会社経営とか、とにかく色々なことをはじめるのだがいつも困難にぶち当たる。そのときに「クマッタなぁ……」と困り顔で頭をかく姿が意匠になっているクマのキャラクターらしい。
こういうタイプは色々と手を出すなよ! と僕でさえ思ってしまうわけだが、どうも老若男女問わず人気があるらしい。確かに、シンプルな顔や茶色を基調とした色合いは男性にも抵抗が少ない気はする。
ストラップは一旦外して机の上に置き、緑茶を流し込む。
さてと。泉西先生とは話ができた。残りは美月だ。僕の極秘の美月統計情報によると、泉西先生登場の後に美月が登場したことは一度もない。よって、早くとも明日以降でないと会えないという結論になる。
今日はもう帰ってしまうか。いや、生徒会が抜き打ちチェックに来て「活動の実態がない!」などとこれ以上マイナス要因を増やされたらたまらないか。すると、ちょっと駒を並べておくくらいはしておいた方がよさそうだ。
というか、部員一人だけの時に見られたらまずいよな……。一日ならまだしも、毎日毎日来られたら実質的に僕一人だとばれてしまう。事態収束までは、毎日ある程度は顔を出してもらうようにお願いをしなければ。
「あぁ、美月ぃ~」天を仰いで、思わず虚空に呟く。
「何よ?」
思索に耽っていたため、突然横から返事が来て仰天する。そして、次には恥ずかしさが込み上げてくる。
僕の発見した法則はあっさりと崩れてしまったわけだが、いやこれはむしろ天の采配と考えるべきだろうか……。
よし。将棋部に訪れている危機を伝えようと向き直ったが、美月の視線は何故か下を向いていた。
視線の先を目で追ってみると、そこにあったのはクマッタのストラップだった。
「もしかして、これが欲しい……とか?」
「……」
返事はない。しかし、視線は外れていなかった。
「どうせ捨てようと思ってたところなんだけどな」敢えてそういう表現をしてみた。
すると、「なら、もらう」と言って、携帯端末の穴に通し始めた。
作業が終わると携帯端末からぶらさがったクマッタと向かい合って、「……まぁまぁかな」と呟いている。
タダでもらったストラップとはいえ、プレゼントしたものを受け取ってもらい、所有物に付けてもらうということ。
自惚れは百も承知だが、婚約指輪を受け取ってもらえた男性は、きっとこういう気持ちになんだろうなぁと思った。
「この部屋暑いなー」
照れ隠しにそういって近くの窓を開く。下を見遣ると、中庭には部活なのか不明だがそこそこの生徒がおり、男子女子が親しげに話している姿が何組か目に入った。
胸の中が妙にざわつく。
――慎重過ぎるのはもっといけない
――先手必勝
「あのさ」僕はゆっくりと振り返る。
いや、ちょっと待て。僕は、自分自身がコントロールを失い、瀬田桂夜という存在から切り離されているような不思議な感覚に襲われた。こいつ、まさか。しかし、動き始めた自分を止める方法が分からなかった。
「何?」
「俺と……。付き合って、くれないか」
その言葉を待っていたかのように、突然僕の背後から一陣の風が吹き抜けていった。美月は前髪が煽られ、顔を覆っている。そして、風が過ぎた後も姿勢はそのままだった。
あまりに。あまりに唐突過ぎるじゃないか? なんていうことをしてくれたんだ……っ。
自分自身がやらかした奇行に未だに自分自身が一番戸惑っている有様だ。
美月も美月で、せめていつものように「ヒマじゃないから無理」などとあっさりばっさり切り捨ててくれれば、「悪い悪い。ちょっとキザなセリフってやつを言ってみたくてつい」などと笑ってごまかるかと思っていたのに。
「……24時間考えさせて」それだけ言うと、足早に部室を出て行ってしまった。窓を開けてから、本当にあっという間の出来事だった。
後に残されたのは、盤と駒と飲みかけのペットボトルと、脱力しきった恋愛下手な16の男子高校生だけだ。
しばらくの間、窓際からは動くことができなかった。背中には夏の日差しがちりちりと突き刺さってくる。先程の突風は幻だったかのように、今は凪の状態が続いている。
「……総会の話、できなかったな」
やっと出てきたのはそんな言葉だった。
家に帰っても、気分はうわの空だった。夕食に何を食べたかの記憶も定かでない。ピーマンを知らずに食ってたらと思うと鳥肌ものだが。
将棋部の第一部維持の対策検討。琴羽野さんの相談ごと。宿題や予習もろもろ。ギターだってまだ全然上手くなっていない。
色々と進めなければならないタスクがあるはずなのに、一向に頭がそちらに向こうとしてくれない。
なんとなく、リビングにある共用パソコンでインターネットサーフィンを始めてしまった。インターネットは有限さを感じさせないほど、際限が無い世界だ。少し暇つぶしに、と思っていたのに気づけば1時間が経っていたということはざらにある。浦島太郎が行ったという竜宮城とは、インターネットの海の中にあったのかもしれないな、などとくだらないことを思った。
午後8時ちょうどになり、テレビからは威勢のいい声が聞こえてきた。「このあとは、芸能界、スポーツ伝説!」
確か、売り出し中の若手の芸能人が本物のアスリートと混じって特殊な運動競技を勝負する番組だったか。普段はおどけている芸能人の意外な身体能力、普段は真面目なアスリートの意外なバラエティ能力、そういったものが観られるということで幅広い視聴層を獲得している。勝敗を結果が出るまでに送信して、当たれば抽選で商品をもらえるという企画も同時並行しており、こちらも視聴者の底上げをしているようだ。
我が家では家族3人が一緒に観る(ただし、父に関しては奇跡的に定時あがりできたときのみ)、数少ない番組の一つだ。今は野球がシーズンの真っ最中なので、父の観る動機になる野球選手は登場しないが、なんとなくこの時間はリビングにいるような感じだ。そういうリズムになっているのだろう。
『伝説』という単語で、昼間に福路くんが話していた『都市伝説』を思い出した。えーと、何だったか。中央駅の壁とか童謡とかだったかな。
うろ覚えなので、それらのキーワードと『都市伝説』で検索を掛けてみた。32件。思っていたよりも結果は多くないな……。とりあえず、一番上に出てきたページを開いてみた。
随分シンプルなページだった。インターネット黎明期に自分でタグを組んで作られたページだろう。逆に言うと、そのくらい前から存在していた都市伝説ということが言える。
トップページの下部にシンプルな一覧があった。項目がリンクになっていて、詳細はその先で見られるようだ。ざっと眺めると、『中央駅の壁』『眠れずの薬』が眼に留まった。福路くんが話していたものだ。あれ? もう一個くらいあったような気がするけど、なんだったか。
もう一度、上から順に眺めていくと、おや?と思われる項目があった。
『ちいさなもりのおおきなき』の悲劇
奇しくも、久々に昨日耳にした童謡の名前がそこにあった。それにしても、悲劇って一体……? あんなに無邪気な童謡にどんな秘密があるのだろうか。急にドキドキとしてきた。あぁ、これがもしかして都市伝説の魅力ってヤツなのだろうか。福路くんと蒼井さんがハマる気持ちが少し理解できた気がする。
はやる気持ちを抑えながら、クリックをする。現れたページは次のようなものだった。
今では、多くの人に親しまれている童謡『ちいさなもりのおおきなき』であるが、その歌詞は作者の意図に反し大きく改変されてしまっている。
本来の歌詞では、〈おおきなき〉は人によって切り倒されて切り株にされてしまう末路となっているのだ。当時、商工業環境と住環境のために山地の整地や干潟の干拓などを国策で行っていた。童謡制作の依頼をした教育機関としては、他の組織との軋轢をなるべく避けるため改変を求めた。
作者は抵抗を続けたが、様々な工作により、最終的には同意をさせられた。
同じページ内に、その本来の歌詞が載っていたが、長さも内容も確かに僕がこれまで歌っていたものとは違う箇所が目立つ。
元々、わらべ歌や童謡は物悲しいメロディーのものが多い。『とおりゃんせ』『かごめかごめ』などがいい例だろう。昔の子供達はよくこんな歌を歌っていたものだと感心する。
『花いちもんめ』『めだかの学校』『しゃぼん玉』などメロディーが明るめの歌でも、少し見方を変えて歌詞を読んだとき、背筋に寒いものを感じるものもある。童謡は、物心ついたときには、記憶の奥深くに刷り込まれているものだ。それが実は全く異質のものだったという恐怖心。例えば、化け物から追われて安全な建物の中に逃げ込んだのに、その中には別の化け物が既に潜んでいたような感覚だろうか。
この『ちいさなもりのおおきなき』の話は後者の方に近い感覚だ。
まぁしかし、都市伝説は都市伝説。裏づけが得られないからこそ、伝説であり噂どまりなのだ。
僕は次のページ、『中央駅の壁』をクリックした。こちらは、文字よりも画像が多いページだった。その画像を見てあっとなる。
この中央駅というのは、隣町の中央駅のことだったのか。全国区であろう童謡の話と同じレベルでページが作られていたから、少し虚を突かれてしまった。
先程、ヒット数が32件程度だったのもこの都市伝説がローカル過ぎるためだったのか。
内容はというと、A3出口の近くの壁が僅かに周囲の色と違うのだという。これが、工事中に起きた事故を隠蔽するためだとか、隠し部屋があるだとかいう伝説となっているらしい。記憶にはあまりないが、実際に掲載されている画像を見る限りでは確かに異なっていた。今度、駅に行ったときに見てみるかな。
トップページに戻り、なんとなしにページの右上を見ると「By 29652」とあった。最初はアクセスカウンターかなにかかと思っていたけれど。
ふくろこーじ = 29652 ?
もしかしてこれは、福路くんのページなのか? 思い返してみると、文体とかセンスが福路くんぽい感じがしてくる。
と、そのときテレビの方から「みなさんこんばんは! 今週も張り切ってまいりましょう。芸能界、スポーツ伝説!」という音声が聞こえてきた。午後8時ちょうどになったようだ。
食器洗いを済ませたらしい母がエプロンを外して、リビングにやってきた。手にはピーナッツ入りの容器を持っている。母の大好物だ。これから、テレビ番組を見ながら食べるつもりだろう。
父はいつものようにシステム手帳のリフィルの整理を黙々としている。傍から見たら、何が面白いのか分からないが、本人いわく『趣味の情報整理をしている』らしい。
テレビ画面の中では、新進気鋭の芸人が池に浮かべられたビート版を走り抜けるといった競技を行っていた。踏んだビート版が沈む前に、次のビート版に進みと繰り返していくわけだ。一見すると非常に単純明快、簡単そうな競技だが、チャレンジャーは次々に失敗して池に落ちていく。
動かなければ、沈んでしまうと思って動いた。しかし、動いた結果僕は沈んでしまった。
母は、僕の様子に気付くはずもなく、時々笑い声を上げながらピーナッツを頬張っている。
僕はというと、笑い声を上げるような気持ちには全然なれなかった。いつも楽しみにしている番組なのにな……。
きっと気持ちの中に、しょっぱいものが混じってしまったせいだろう。まさしくこれが本当の沸点上昇だ。
番組がCMに突入しても、母と僕はそれぞれ画面を向いたままでテーブルの腰掛けていた。
「女の子の心って、どうしたらを掴めるんだろうなー」
答えを特に期待していたわけではなかったが、気持ちを紛らわすためだけにそんなことを聞いてみた。
「そうねぇ……。『君がいないと、僕の人生は暗黒物質だ』とか訳の分からないことを言ってみるとか?」
なんだそりゃ、と思うのと同時に、父がばつの悪い表情を浮かべながら「さて、風呂の湯加減でも見てくるか」とリビングを出て行く。
そういうことか。わざとらしい物言いに思わず苦笑する。我が家の風呂の水温は自動調整式のはずだ。
「お母さん、こう見えて、可愛くて頭良くて、運動神経も良くて、人脈も広くて、そりゃもう超絶女子だったのよ?」
「……へいへい。それがなんでまた、あんな父と一緒になったのか、お聞かせ願おうか?」
「いいわよ。あれは大学1年の頃……」
あっさりと応じられて、少し戸惑う。しかし、今まであれこれ突付いても飄々とかわされてきた両親の馴れ初めの話だ。興味がないといえば嘘になるし、今は気を紛らわすことになると思って、静かに耳を傾けていることにした。
僕の母、いのりは大学入学直後、学部の新歓コンパに参加していた。
新入生歓迎とはあくまで名目上のことで、その実態は新入生を上級生が酒で酔い潰させるという悪習であった。当時は今ほど娯楽が多いわけでもなかったし、「自分達がされたから、俺達もやる」そういう悪循環が格好悪いと思われていない時代でもあった。
いのりは予行演習として、事前に酒を少し飲んでみた。その結果、ある程度飲める体質であることを知っていた。
下級生全てが酔いつぶれてしまったら後始末も大変であり、派手にやりすぎると大学側としても黙認してくれない面があり、上級生から狙われる人数はある程度の人数に限られていた。
逆に、最後まで生き残った新入生は『ツワモノ』としてその後一目置かれることにもなる。いのりは上級生に促されるまま、ひたすら飲んだ。
しかし、飲める体質といっても当然限界はあるし、本当にザルのような酒豪も世の中には存在する。
酒の恐ろしいところは、『自分が酔っている』と判断する部分でさえ麻痺させられてしまうことだ。とりわけ、大勢の人と一緒に飲むときは自分のペースが乱れてしまうため、この現象も現れやすい。
この時のいのりも例外ではなかった。知らず知らずのうちに、身体は傾き始め、眼はとろんとし始めていた。
「ウーロンハイのひとー?」
「あ、はい!」
自分の頼んだ飲みものを呼ぶ声が聞こえたので、いのりは応じた。
手を上げたいのりの手元に、すっとグラスが置かれる。
「ほら、おかわりがきたよ! いのりちゃん、ぐっといって! ぐっと!」
「は、はい」
脇にいた体格のいい角刈りの大男が促すのに併せて、一口飲む。
(ん? あれ、これ……?)
いかに酩酊状態になったからといって、アルコールが入っているか否かくらいの判別はまだ可能であった。
今飲んだウーロンハイだと思ったものは、ただのウーロン茶だった。
「ん? どうしたのー?」
「いえ、美味しいです!」
「本当に強いなー。オレも負けてられないぜ~」
一体、何が起きたか分からなかったが、変な反応をしてこれ以上飲む量を増やされても面倒だと思い平静を装うことにした。
一杯とはいえアルコールの入っていない飲み物を飲んだせいか、少し頭と胃の方が落ち着いてきた。次はグレープフルーツサワーを頼んだ。
しかし、その変な現象は再び起こった。届いたのはグレープフルーツジュースだった。
(一体、どうして……?)
いのりは毎回グラスを運んでくるのは同じ男子上級生であることには気づいていた。印象的な腕時計をしていたからだ。
次に、日本酒のグラスが運ばれてきたとき、いのりはその男の顔を窺った。
むすっとしたへの字口、服装は野暮ったくて、どう甘く採点をしても女子ウケする第一印象ではない。
男もいのりの視線に気づいた。
「……こんなことで、無理すんな」
いのりにだけ聞こえるギリギリの声量でそれだけ言って、グラスを置いて去っていった。
いのりは、周りの人が日本酒と呼んでいる、ただの水を飲みながら考えた。一体、あの人は何者なんだろうか、と。
そのあと間もなく、先程の男子上級生が急性アルコール中毒で倒れたという話が伝わってきた。
いのりの集団はもとより店内も騒然となった。当然ながら、散会の流れとなりいのりは開放された。
「ったく、やらかしやがったの、瀬田かよーっ」「酒飲めねぇ奴はコンパくんなよっ」そして、周囲にいた上級生は、ソフトドリンクばかり飲んでいたはずなのに倒れるとは、摩訶不思議・迷惑千万の呆れたやつだと悪態をつきながら店を出て行った。
いのりは直感した。恐らく、私の飲み物と同じような色の飲み物を注文し、それを交換し続けていたためだろう。
その後、二人はどちらからともなく近づいて、その末、付き合うことになった。学部内では、あまりに不釣合いな二人に、あらぬ噂を立てられることもあったが卒業まで貫き通したのだった。
「まぁ。今、総括したみたら、一番かっこよかったのは、結局その時だけだったわね」
「おいおい」
「でも、それでいいんだと思う。あの人は私にとってエアバッグみたいな存在なのかもしれないと思うわ。普段はありがたみも特に感じないまま近くにいるだけだけど、本当に困った時には身体を張って守ってくれる。私にはそれが一番大事だったんだろうね。世の中には、『いつも愛していてくれないとイヤだ』って人や『年収が低いと論外』って人も多いけど。今、不幸でないのは事実だし」
自ら淹れた緑茶を啜りながら、僕の顔をじっと見つめてくる。
「あんた、振られたでしょ」
「……あっさり当てるなよ」
馴れ初め話を語ったのは、親心か。
「ナナちゃんのときはこんなに落ち込まなかったのに。よほど逃げられた魚が大きかったのね」
「……」
「気分をすぐに切り替えることね。他の失敗ごとも同じだけど。世の中の半分は女の子なんだからさ」
「……残りの半分は競争相手じゃん」
まぁ、気分をすぐに切り替えるのは間違っていない気がする。過去は変えることができないのだから。認識の方を変えるしかない。
元から、高嶺の花だったのだ。今まで、お近づきになれていた期間があっただけでもプラスに思わなければ。
僕、今日無事に寝つけるかな……。
小説『Sum a Summer =総計の夏=』(1/5)
*****
ちいさなもりのまんなかに おおきなきがありました
ひとやおはなやどうぶつが もりにやってくるまえから
きは みまもった いつまでも みまもった
ちかづくことなく はなれることなく
きにはおおきなえだがあり おおきなはっぱもありました
あついなつにはかさになり みんなひるねにきたのです
きは みまもった いつまでも みまもった
わらうこともなく おこることもなく
ちいさなもりのおおきなきは あおぞらにむけのびていき
ひろいだいちをみおろして きょうもしずかにわらってる
きょうもしずかにわら っ て
る
童謡『ちいさなもりのおおきなき』より
*****
第一章 『7月1日(火)』
本日、7月1日。晴天なり。
6月生まれの人には非常に申し訳ないが、ひとこと言わせてもらおう。6月って、じめじめとして、祝日もない、地獄のような一ヶ月だったよ。
そんな地獄がついに終わり、僕の心は晴れ渡っていた。
制服も夏服になり、高校生活初の夏休みも確実に近づいてきていることも理由の一つに間違いはないが、第一番の理由は――
「期末テスト、終わったー!」
この一言に集約できよう。
昨日まで丸々3日かけて行われたテスト期間が終わり、僕だけでなく他の生徒や教師までも言いようの無い開放感に酔いしれていた。
え? テストの手ごたえ? ……黙秘権を主張します。
僕が通う大矢高校は、一年間を4つに分ける『四期制』を導入している。
多くの大学は前期と後期に分かれているし、企業の中には中間と期末だけでなく四半期決算を採用するところが増えてきているのでそのリズム感を高校のうちから身に付けさせようというのだとか。
また、学校のカリキュラム等も四半期末に見直しや改善を行い、時代に即した教育と学習の機会を得ることができるようだ。
テスト期間中は多くの部活動が休止状態となる。大矢高校は文武両道を謳っており、赤点は問答無用で補習だ。よって、スポーツ一筋の生徒でもなんとかそれだけは避けようと必死になっていた。
当然、将棋部も軽音楽部も休止状態だった。
1、2、3、4――2、2、3、4――
ヴォーーーー……
運動部の掛け声や、吹奏楽部の楽器の音など、以前の賑やかな放課後が久々に戻ってきた感じだ。
部活の解禁日。僕は迷わず、将棋部の部室に行くことを決めていた。目的は一つ! 片思いの相手と逢いたいがためだ。
高校に入ってから間もないうちに、僕は好みの女の子と出逢った。しかも幸運なことに、部員が二人きり(少し厄介な顧問がいるが……)という状況だ。
ところが、その女の子――織賀美月とは5月、6月に数度しか逢えていない。
元々、美月が部活に顔を出すことが珍しいことが一因だ。月に9、10日来るか来ないかという頻度のようだ。法則性は未だに確立されていない。(瀬田桂夜リサーチコーポレーション調べ)
一方、僕の方はというと、軽音楽部との掛け持ちをしている。音楽は高校から本格的にはじめることになったので、ここまでは軽音楽部7:将棋部3くらいの割合で活動していた。
さらに、僕がテスト期間直前まで長期スパンで体調を崩してしまい、病欠や早退を何度も繰り返してしまっていた。
せっかくのチャンス、貴重な2ヶ月を浪費してしまった僕の意気込みがお分かりいただけただろうか。
しかし、意気込んでいても逢えるとは限らない。特に約束もしているわけでもなし、かといって行かなければ逢う可能性はほぼゼロだ。
将棋部の部室に向かい、ガラガラとドアを開けるが、中には人はいない。
(そうそう上手くはいかない、よなぁ)
こればかりは仕方がないことだ。気長に待つしかない。盤と駒を机の上に置き、僕は椅子に腰掛ける。
鞄からマイ水筒を取り出して一口飲む。本日は、マテ茶だ。やけにマニアックなのは父のせいである。
簡単な式で表すと次のようになる。
父が健康志向を主張 + 母は各々作るのが面倒だから二人とも同じもの飲みなさい = 毎日健康茶
最初は「なんだこの苦い汁は!?」と思っていたのに、慣れてくると心が和むようになるのだからニンゲンって恐ろしいよね。
さて。
将棋は、基本的に二人でするゲームだ。一人じゃどうしようもない。ここに、将棋部における根本的問題がある、と認識する。
将棋部的にも僕的にももう一人の部員が足繁く来てくれればこの上ない解決方法であるが。
当座はパソコンでも導入してみようか、と考えてみる。最近の将棋ソフトはよくできているものが多い。アマチュア強豪レベルならば良い練習相手になるだろう。
一時期、将棋をやめるきっかけの一つにもなったコンピュータ将棋を導入しようと検討するのだから不思議なものだ。
ただ、自宅のパソコンを学校に持ってくるわけにも行かないし、携帯端末の処理性能では性能不足だ。
顧問の泉西先生に学校の備品でパソコンが借りられないか交渉してみるかな。職員室に押しかけようかとも思ったが、今はテストの採点期間なので生徒の入室はNGだ。
美月とすれ違いになってしまうおそれもあるから、ここは詰将棋でもして待ちの戦略をとることにしよう。
詰将棋とは、端的に言ってしまえば『将棋の駒を使ったパズル』だ。
指し将棋と同じく、相手の王将を詰める、というのが目的なのだが、いくつか変わったルールがある。ざっくり言うと次のような感じだ。
その1、必ず王手を続けること。
その2、自分は最短で詰めることを目指し、相手はできるだけ最長手数で逃れようとすること。
その3、盤上に『飾り』のような無駄な駒を配置しないこと。また、持ち駒も余らせないこと。(これはつまり、詰将棋作成者へのルールともいえる。盤上に無駄な駒を配置したり、持ち駒を全て使い切るように作らないといけない)
中には、週間少年誌のお色気漫画の展開並みに「絶対こんな状況、ありえないから!」と叫びたくなるような問題もあるのだが、それはそれ、ご愛嬌だ。
ただ、パズルと侮ることはできない。アマチュアは勿論、プロの棋士でも終盤力のトレーニングには詰将棋はもってこいなのだ。
盤と駒、対戦相手がいなくても本が一冊あればできるし、隙間時間を有効活用することもできる。
僕は直感で指すことが多いので、緻密な読みが必要となる終盤が相対的に苦手項目といえる。
(この本もやっと半分まできたか)
確か、小学4年生くらいの時に親に買ってもらったような気がする。一時期やめていた時に封印していたものを引っ張り出してきたのだ。
小学6年生の頃に全部解けているだけの実力があったら、あの全国大会で江辻に勝ち、優勝して自分の進路も随分と変わっていたのだろうか。プロ棋士を目指していたりして。
いやいや、考えてもしかたない空想だ。
大矢高校に入って、美月とも出逢えて、今は音楽と将棋(とちょっとばかりの勉強)の両立を目指しているところなのだ。
決して遠回りしているわけじゃない、と考え直す。
その時――
ガラガラというドアの開く音と共に「お、いる」と懐かしい声を聞いた。
手許の本から視線を移すと、そこには期待通りの姿が立っていた。もう一人の将棋部員、織賀美月(夏服バージョン)だ。
女子の制服は、ブレザーにネクタイだったのが半袖シャツとリボンに変わる。ちなみに、男子は半袖になるだけだ。
(おぉ……、夏服も……いいなぁ)
美月は部屋に入ってくると、手近な机にバッグを置いた。
「センセから聞いたよ。体調もう平気なの?」
「あぁ、うん。この通り」
僕は両手を挙げて応じる。
「……? それ、なに?」
手に持っている本に気づき僕に尋ねてくる。
「これ? 詰将棋だよ」
「爪将棋……?」
……うーん、なんだか勘違いされている予感がする。
よく考えたらこの間まで将棋のルールも知らなかったわけで。知らなくても不思議ではないわけだが。
物心ついたときから将棋に接してきた人種としては、カルチャーショックではある。
将棋部員なのに詰将棋を知らないのはさすがにまずかろう、と例によって丁寧に正確に詰将棋というものを教えてあげた。
さすがに吸収は早かった。本の前半の方の問題を試しに見せてみたところ、あっさりと解いていってしまう。
「暇つぶしには結構いいと思うよ。この本貸そうか?」
「常に暇がないから、いらない」
……そうですか。これが美月の標準スタイルだと認識済みなので腹も立たなくなってしまった。RPGの装備に『僕の堪忍袋』が登場したら、さぞや守備力が高い設定になっていることだろう。
「アローハー! 諸君! 元気KAI!?」
そして、……来たーーーー。
渋い和服を着込んでいるのに、このヘリウムガスと良い勝負の軽さ。全くついていけない、否、ついていく気になれないノリ。
大矢高校の現代国語教師であり、非常に残念なことに、この将棋部の顧問である泉西先生だ。愛用の扇子をパタパタと仰ぎながら部室の中にずんずんと入ってくる。
扇子には〈黙って俺についてこいっ!〉と書かれている。誰がついていくもんですか。
「ははは、俺のスペシャルな問題はいかがだったかな? まさか、筆者が作品を書いたときの娘の気持ちを問われるとは思わなかっただろう」
「あんなメタな視点の問題、アリなんですか? 泉西先生も答え分からないでしょ」
「うん。だから、ちゃーんと文章になってれば全員丸だぜ。問いに対して何にもレスポンスをしないヤツは社会で生きていけないぜ~、という、実は俺からのありがたい処世術伝授問題なのだ!」
なんだか、相変わらず屁理屈街道爆走しているなぁ。一体、この高校の教師採用基準はどうなっているのだろう。
「と、俺のすごさをアピールしている場合じゃなかった! 部長よ、総会にお行きなさい!」
「ぶ、ぶちょ……うですか?」
「そうだよ。何を言っている、部員はお前達だけだけだろうが。瀬田は将棋だけが取り柄だろう。だから部長手続きをしておいてあげたぞ」
「だけ、は余計です! って確かに部長はどちらかになりますけど……」
まぁ、美月は頼みに頼んでも部長をやるようなタイプでもないだろう。致し方ないところだ。
と、総会って、一体なんだろう。
見るとニコニコしている泉西先生と眼が合う。
「総会って、一体なんだろうって顔してるな?」
「心を読まないでください!」
泉西先生はどういうわけか、人の心を読むという反則的な特技を持っている。
「では、丁寧に教えてやろう。まず、物凄い偉い存在が『ヒカリ、アレ!』と申されたところから物語は始まる」
物凄い偉い存在が何故カタコトだったのか突っ込もうか迷ったが、やぶ蛇と思い「えーと。ものすごく丁寧じゃないのでお願いします……」とだけ返す。
泉西先生は「生き急いでやがんなー」とぶつぶつ言ったが、とりあえず説明はしてくれた。律儀なことにものすごく簡単に。
まず、部活は第一部と第二部に分けられているのだという。
簡単に言ってしまえば、第二部は愛好会(部活もどきのようなもの)で正式な部活ではない。部室も共用室を交代で使用しなければならない。
対する、第一部は専用部室を与えられ、予算も受けとることができる。その他、秋の学園祭のスペースなどでも優遇も多い。
総会は、その第一部の全部活の部長が集まり、予算や要望や情報共有を諮る場いうことだった。
将棋部は近年部員ゼロだったが、顧問である泉西先生が代理で出席していたのだという。泉西先生の暗躍があったのか不明だが第一部に留まり続けていたようだ。
「俺、これからテストの採点しなきゃいけねーしさ。採点遅れると給料減額なんだよ! てなわけで、ヨロシク頼むぜ部長!」
そういうと、砂嵐のように教室を後にしてしまった。この手の素早いモンスターは、倒すと経験値がたくさんもらえるのが相場だが、きっと泉西先生を倒しても得られるものは少なさそうだ。
「ここ、かー」
見上げたプレートには〈大会議室〉と書かれている。
結局、僕が総会に出るということで、美月は帰宅してしまった。
せっかく、久々に訪れた逢瀬だったのに……。そういえば、もうすぐで七夕だなあ。
ドアはきっちり閉まっており、中は伺い知れない。意を決して中に入らなければならないわけだが、ドアを開けた瞬間に上級生の視線が集中したりするのは勘弁だ。
3年生はきっと互いに見知った顔が多いだろう。そうでなくても今年度の総会は2回目だから、基本的には僕一人だけが『新参者』のはずだ。
そう思うと、少し心音が高鳴り始めてくる。
(こういうの、ホント向いてないんだよな……)
しかし、そんなこといっていたら、音楽ライブなど夢のまた夢ではないか。
高校に入って、どんどん自分のダメなところを変えて生きたいと思っているんじゃないか。自分自身を騙し騙し奮い立たせる。
(なるようになれ、だっ!)
ドアを恐る恐る開けると、中にはまだ数名しかいなかった。心配していた視線も特に突き刺さってこない。
(あれ? 場所、間違えてはいないよな)
辺りを見回す。四角に並べられた長机の上を良く見ると、『●●部』といったアクリル板が席ごとに並べられていた。
場所に間違いはなさそうだが。少し当惑の表情で入口に立ち止まっていると。
「10分後には始まるよ。みんな時間が惜しいから、いつもギリギリになって一斉に集まって来るんだよ」
脇にいた女の人が丁寧に教えてくれた。
と、あれ?
どこかで会ったことがあるような、ないような。誰かに似ているような、似ていないような……。
それは相手も同じだった。僕の顔を見て、何か記憶の糸を手繰り寄せているようだ。
「あ。キミ、もしかして瀬田くん?」
「えっ、あっ、そ、そうですけど……?」
不意を突かれ、戸惑ってしまった。まさか、三年生の女の先輩に名前を知られているとは思わなかった。
良い噂なのやら、悪い噂なのやら。
そして、今度は僕の記憶と推理の糸に手ごたえが合った。
「あっ、勝田くんの、お姉……さん? ……ですか?」
「ピンポーン!」
改めてよく見てみると、キリリと締まった面持ちやスポーティな体格は勝田くんの持つ雰囲気とよく似ていた。
ちらっと机上を伺うと、『女子バスケ部』とあった。なるほど、スポーツ一家だなぁ。
「ダイから将棋部の瀬田くんの話は聞いてたんだよ。で、今回二回目であるはずの総会で挙動不審アンド一番上のボタンまできっちり閉めた男の子とくれば……ね。うちの推理もなかなかのもんでしょ!」
「あ……、はっ、はい。そうですねっ!」
「ダイがべたほめでさ。あいつ、この間の件で小遣いアップしてもらって、本当うらやましいわー」
この間の件――勝田くんのおじいさんがお父さんに出したメッセージのことだ――で小遣いアップできたのかぁ。それは、僕としても羨ましい限りの話だ。
勝田くんのお姉さん、勝田ルイ先輩はとてもハキハキした人だった。大矢高校の話、勝田家の話、とめどなく話をしてくれる。
基本的に相槌だけ打っていたのだが、そのおかげで先程までの緊張は自然と解けていった。
突然、ルイ先輩はふと何かを思い出したように「ちょっと、試させてもらっていいかな?」と言ってきた。
「試す、ですか?」
「そうそう。あ、難しく考えなくてもいいの。ちょっとしたクイズみたいなもんだから。もしいい答えができたら……あとで『ごほうび』あげる」
「クイズ……?」
クイズというより、正直なところ、その後の『ごほうび』のほうが気になるのだが。さっきまでは気にしていなかった、ルイ先輩の艶やかな唇がとたんに気になってくる。
バカ、そんなはずないだろ! 冷静になれ。十秒……二十秒……一、ニ、三……。って『秒読み』じゃ逆に焦ってしまうじゃないか!
ルイ先輩はそんなカオスな心境になど気づくことなく(気づいてくれないほうがありがたい)話を続ける。
「うちの家の前って自動販売機があるんだけど、ちょっと妙なことが起きたんだよね」
確かに、勝田くんの実家の前には自動販売機が置いてある。ビールとかタバコではなく普通の飲料系だった気がする。
ルイ先輩の話を要約するとこうだ。
・飲料の値段は全て100円。
・それなのに、毎週の回収時に調べてみると、10円が50枚近く入っている。
「これ、実はもう答えが分かっていてね。聞いたら、なーんだな感じなんだけど。どういうことだったか分かるかな?」
これがクイズの問題、というわけか。
10円が50枚ということは、飲料5本分だ。一週間に、5人くらいは全て10円玉で買っていく人がいてもおかしくない気もするけど……。
しかし、ここで問題を出してくる以上、普通の答えではないのは確実だろう。
「すみません、質問はありですか?」
「そうだねぇ。じゃ、3回までオッケーとしよう」
3回か、それでも随分とありがたい。慎重に使いたいところだけど、まずはこれは聞いておきたい。
「その10円玉って、製造年はバラバラでしたか?」
「ふむ! なかなか、いい質問だね。製造年はバラバラだったよ」
もし、製造年が全て同じだったのならば、『お釣り用に銀行でもらった硬貨の棒を蔵出しにした』とかかと思ったけど。
ジュースは売れていたのだろうか。ジュースが買われずに、自販機の硬貨だけが入れ替わっていたとしたら、偽造硬貨を入れ替えてたなんて話もあり得るかも。
あとは、貯金箱に貯めていた10円を一気に大放出した人がいた、とかだけど、10円玉を飲料を買うことだけに使い続けるだろうか。
「もしかして……学生、細かく言うなら小学生が20円ずつ出し合ってジュースを買っていたとか……? あれ!?」
気づいたらそう口にしていた。それには自分自身が一番驚く。質問のチャンスがあと2回残っているというのに、勝手に〈跳躍(リープ)〉してきた考えを言語化してしまっていたのだから。
次に声を発する時は『質問その2』が来る、と構えていたのか、ルイ先輩もきょとんとした表情を浮かべていた。しかし、すぐに「続けてみて」とだけ返してきた。これは後に退けない雰囲気だ。
僕は、まだ固体になっていなかった気体のような自分の考えを少しずつ言葉にしていった。
まず、50枚の内訳を10枚×5日と仮定すると、『平日のみ』購入されると推測できそうだ。
とすると、そこを通る学生か会社員かが怪しいが、一人で10円を毎日10枚も入れ続けるとすると奇妙すぎる。
複数人が10円を10枚分用意していたならばまだ現実的と考えられる。そう、10人が10円ずつ出し合うならば現実的だし、毎日続けることも可能だろう。
さらに、10円を恒常的に持っていそうな――例えば小遣いとして10円玉を毎日持っていそうな――年齢層は小学生ではないだろうか。
10円で缶の10分の1だけを買うことはできない。しかし、一旦買った後、飲料を10等分に配分しなおすのならばその希望は叶う。
あとは、10人で10円ずつか、5人で20円ずつかということだけど、登下校のグループとするならば5人の方が妥当そうに思えた。
「驚いた……。ほぼ正解だね。てか、あの内容だけでこんなにすぐ筋の通った推理ができるなんて、上等上等。気に入ったよ!」
ルイ先輩の補足によると、小学生の人数は5人で、買った後は山分けするのではなくジャンケンをして勝った人だけが1缶分飲める仕組みだったらしい。最近の小学生はなんとも競争心旺盛なことだ。
それはそうと。気になるのは、『ごほうび』だが……。
見ると、ルイ先輩はずいぶん満足したようで、僕の背中をバシバシ叩いたり、大きく頷いたりしている。
「よし、約束どおり『ごほうび』あげるよ」
言うなり、ルイ先輩が顔を僕のほうにすっと近づけてくる。
おおっ。ニーチェさん、違います。神はまだ生きてます!
いや、しかし僕には美月という想い人がいるというのに許されるのか。片思いじゃないのかという指摘は却下します。そう、カレーは好きだけど毎日食べていたらありがたみが薄れちゃうでしょう? 人間、ハヤシライスが食べたいときもある。ハヤシライスを食べることでカレーの美味しさが再認識できるというか。比較が大事なんです。人生でカレーしか食べたことがない人は本当の意味で「カレーが一番」と認識できないのです!
心の中で、小さな僕が美月の写真を握り締めている僕の群集に向かって大いなる力説をしている。ルイ先輩の顔はなおも近づいて……。
すっと、僕の左耳の脇にそれた。そこで、「……味方してあげるから」小声でそういった。
(えっ、ど……)
どういうことですか、と声にしようとして周りの様子に気づく。推理と話に夢中になっていて気づかなかったが、既に議長席を含めたほぼ全ての椅子が埋まっていた。
「そろそろはじめます」
そんな声が聞こえたので、とりあえず「ありがとうございます」と返した。ルイ先輩の真意が分からぬまま、『将棋部』の席に急いだ。
「定刻になりましたので、第二四半期の部活動総会を始めさせて頂きます。生徒会、副会長の辰野です。本日、司会兼議長を務めさせて頂きます。
まず、奥地生徒会長よりご挨拶をお願いいたします」
辰野副会長に促されると、制服の一番上のボタンもきっちりと締め、高校生としては異色の七三分けをしている男子生徒が一同に礼をした。
「生徒会長の奥地です。皆さん、本日はお忙しいところご足労感謝いたします」
あれが有名な奥地先輩か……。
見た目はあまりイケていないが、常に学年3位以内をキープする秀才だ。将来は父親と同じ弁護士になるのが目標で、それも難しくないのではないかと評判される秀才だ。
「本日は第二四半期の始まりに伴い、各部への報告および挙げられた要望に対する議論をさせていただきたく。まずはお手元のアジェンダをご覧願います」
手元のレジュメは次のように書かれていた。
1.生徒会からの連絡事項
2.各部からの活動報告・要望等
3.次回開催日について
(2の活動報告ってなんだろう……)
まさか、この大勢の3年生の前で何か話をしなければならないのだろうか。そう思うと、少し手のひらに汗が出てきた気がする。先生、聞いてないすよ!
「まず、『生徒会からの連絡事項』です」
奥地先輩の話が淡々と続く。
「今月は防犯強化月間です。各部、活動終了時間の厳守、および活動後の施設施錠を徹底願います。また、今月下旬から夏期休暇が始まります。遠征等で追加の部費申請が必要となった部は本日の資料に添付した申請書に記入し、逐次申請するようお願いします。生徒会にて、学務経理課に仲介いたします……」
内容はいたってシンプルなことばかりであった。となると、先程ルイ先輩が言っていた『味方したげる』とは一体何を意味しているのだろう……?
「……連絡事項は以上です。続きまして、各部からの活動報告・要望等をお願いします。まず、男子陸上部からどうぞ」
奥地生徒会長に促され、色黒短髪の非常に体格がいい男が返事をする。
「男子陸上部です。春季大会にて、3名が地域予選を突破、うち1名が――」
はぁ……、さすがというかなんというか。大会でしっかり結果を出しているのだ。
「要望は特にございません。以上」
うーむ、この分で行くと僕も将棋部部長としてなにか発言をしなければならないのか。段々気が重くなってきた。
そして、ついに発言の番が巡ってきた。
「しょ、将棋部です……。えーと、その」
視線が一斉に注がれる。耳たぶや目頭が熱くなっていくのを感じる。1対1ならば知らない人とでもそれほど緊張せずに話せるのだが、大勢相手だとどうにも不得手だ。
「活動は……部員が集まりましたので、始めはじめたところです。あー、……えーと。た、大会は夏休みに、個人戦に参加する予定でございます――」
なんとか話しきった……。こんな緊張はいつ以来だろう。あ、美月の走っているのを見て叫んでしまった英語の授業中か。じゃあ、意外に最近だったか。
椅子に腰掛けて、隣の囲碁部部長が話し始めるとやっと終わったという実感に包まれた。発言が終わってしまえばなんということはなかった。あとは、聞きに徹するだけでよさそうだ。他の部長はさすがにみな慣れた様子で報告をしていき、最後の部長までつつがなく終わった。
「第一部の活動報告は以上ですね。……では次に要望等ですが、まず第二部の白物家電研究部から昇格申請があがっております」
白物家電? 洗濯機とか冷蔵庫とかのことだよな……。高校生が何をやってるんだか。思わず苦笑する。
「……そこで、近年の実績を踏まえて将棋部を降格として入れ替える起案をいたします」
浮かべていた苦笑が、そのままフリーズする。
(……えっ?)
今、降格とか聞こえたような、気がするけれど。降格ってことは、第二部になるってことで、部室が使えなくなる? 部活はどこでやればいいんだ? 美月とはどこで会えばいいんだ?
目の前が放送終了後の番組の砂嵐のようになって、周りの声は膜を通しているように遠く感じる。母に聞いた、貧血の症状に近いような気がする。
落ち着け、落ち着け、落ち着け。
まずは色々と質問をして、状況の把握をしないと抗弁だってできやしない。それにしたって唐突過ぎじゃないか? なんで、こんな大勢の前で、逃げ場のないようなところで言い出すんだ?
落ち着け、落ち着け、落ち着け。
でも、貧血のような症状は治まらない。頭が全然働かない。あの、時間切れで負けた江辻との一戦の後のように――。
(僕、全然成長してないじゃないか……)
そう思うと、情けなくて。なんだか目頭が熱くなってきた。って、高校生にもなって人前で泣いてしまうのか僕は……? それだけはまずいだろう。学校中の笑いものだ。誰か、僕を助けて――
そのときだった。
「すみません、ちょっと発言よろしいでしょうか」
静かな会議室に凛とした声が響いた。その声に、症状が幾分和らいだ。声した方向には手を挙げているルイ先輩がいた。
そして、視界に入っている全ての部長達はみな、拍手の直前ギリギリで手が止まっていた。ルイ先輩の発言が一瞬遅かったら、満場の拍手で掻き消えていたかもしれない。
「……女子バスケ部部長、発言を認めます。どうぞ」
「はい。将棋部については経緯をご存じない方々が多いと思いますので、代わりに補足しておこうかと思います。将棋部は4月まで部員が居ませんでした。そこに、元全国3位の期待の新入生が入ったわけです。それが彼です」
ルイ先輩が、僕のほうに手を向ける。それに誘導されて、会場全員の視線が僕に注がれる。
視線のやり場に困ってつい下を向いてしまったが、僅かに感じた。今まで、好奇の目で見られていた視線の中に「ほう?」という色が混じっていたことを。
ルイ先輩はなおも話を続ける。
「我々運動部と違い、将棋の大会はそう頻繁にあるものではありません。もう少し、せめて半年、実績ができるチャンスを待つことはできないでしょうか」
先程の『味方したげる』の意味を理解すると共に、胸が熱くなるのを感じた。
しかし、奥地会長はあからさまに眉根に皺を寄せ、唸る。「……難しいですね」半ば演技が入っている風情に見えた。
「将棋部なりの事情があることは一理ありそうですが、白物家電研究部のあげた実績に着目すると第一部への昇格には問題がありません。すると、半年の猶予は長すぎるように思えます。生徒会則にも『第一部と第二部の入れ替えについては、公正かつ柔軟に対応すべし』とあります。仮に、将棋部が第一部に相応しいとアピールしたいのであれば、白物家電研究部と同じく第二部の状態で実績をあげて、再度の昇格申請をするべきである。これが生徒会の見解です」
万が一の論駁に備えてきたであろう、朗々とした声が部屋に響き渡った。裁判の判決を受ける人の気持ちって、こんななのかな。まるで他人事のようにと感じられた。
「他に意見はありませんか?」
ルイ先輩と僅かに目が合う。その眼は「力が及ばなくてゴメン」と語っているようだった。僕は、「そんなことありません、十分うれしかったっす」という表情を返す。
青天の霹靂でまだ気持ちの整理がついていないが、きっとなんとかなるだろう。夏の大会への意気込みがむしろ高まりそうだ。大きく一つ深呼吸する。
「発言、よろしいですか?」
議決を唱えようとしたところに、再び声が投げ掛けられた。
「……軽音楽部部長、発言を認めます。どうぞ」
奥地会長は露骨ではないもの不快な様子をわずかに浮かべたが、辰野副会長は表情を変えず淡々と応じた。
声の主は、周りの3年生と比べても一際小柄な男子生徒だった。
そして、その男子生徒の卓上には『軽音楽部』のプレート……って、あんな先輩、いただろうか……? 掛け持ちしている僕が言うのもなんだけど。非常に失礼な話だが、正直、印象が全然ない。
何より気になるのは発言内容だ。果たして、敵なのか味方なのか?
「将棋部が降格の候補となった理由はなんでしょうか?」
奥地会長の眉がピクリと動いた。軽音楽部部長の質問を、生徒会を詰問する内容と捉えたような表情だ。
「周知の事実かと思われますが。第一部の中で、唯一最低要件を満たしていないからです」
奥地会長は言外に質問に価値がないという皮肉を込めて切り返す。しかし、軽音楽部部長は全く動じた様子はない。
「白物家電研究部の実績とはどういったものですか?」
「大きく2点。5月の全国大会準優勝、運営しているウェヴサイトの閲覧数が一日あたり約2万件、です」
「全国大会の出場校数、それとウェヴサイトのユニークユーザーの数はいかほどでしょうか?」
「出場校数は5校。ユニークユーザーは約4000人と聞いております」
僕も含めて、周りの部長達は二人のやりとりを固唾を飲んで見守っている。というより、見守るしかない雰囲気だ。
軽音楽部部長は「ふーむ、なるほど確かに悪くない実績かもしれませんねぇ」と小さく呟いている。奥地先輩も面倒な事態が収束したと断じ、構えを解こうとしたところで、軽音楽部部長は追撃した。
「質問を変えます。白物家電研究部からその申請があがったのはいつ頃の話でしょうか?」
「……5月26日、16時47分28秒。生徒会室にて、白物家電研究部部長から生徒会会長に様式『生ブ管-37』の記入済み書面を手渡しにて申請を受け付けました。……その他にご質問は?」
奥地会長はトドメと言わんばかりに細かな情報を提示した。弁護士の卵に弁論で勝負を挑むのは無謀なのだ。それでも、部長には後でお礼を言いにいこう。嬉しかったのは事実なのだから。
しかし、軽音楽部部長は一瞬考えたあと、こう続けた。
「その頃であればテスト期間にも入っていませんね。臨時総会を開かずに、本日まで起案をされなかったのは何故でしょうか?」
その発言内容に、奥地会長はいち早く渋面を浮かべる。
「白物家電研究部の申請を今日の定例総会で起案したということは、不急と捉えられた訳ですよね。今回、将棋部自体にも事前の通達がされていらっしゃらかったわけですから、対応や決定は同様に、早くとも次の定例総会――10月以降で十分かと思われますが」
そこまで聞いて、僕にも意味が理解できた。だが、よく聞けば詭弁の類だ。うわさに聞く奥地会長もこのくらいで折れる性格ではないだろう。
早速、論破のため声を発しようとしたが、それは室内に突如鳴り響いた拍手に阻まれた。
再び、ルイ先輩だ。
それに同調して、他の部長までもパラパラと拍手をし始める。先程までの論戦を見て、この場を早く収束させるのを望む者が大多数だということの証左だった。我々は早く部活に戻りたいんだというオーラも感じる。
また、先延ばしになる間、当事者間で問題が解決する可能性もありうるという目論見もそれなりにあるのだろう。当事者たる僕も、先延ばしは大いにありがたいので、少し遠慮がちに手を叩いてみた。
奥地先輩は歯を食いしばり、手短に「……異論はありません」と引き下がり、手短に次会開催日を通達するとあっさりと散会を表明した。
教室から人が次々に出て行く。彼らにとっては、将棋部の浮沈も所詮は対岸の火事だろうし、早く部活に戻りたい気持ちでいっぱいなのだろう。
奥地会長も足早に去っていった。
残ったのは、机上のアクリル板を片付ける生徒会の面々を除くとルイ先輩、軽音楽部部長と僕だけになった。
「ルイ先輩、部長さん。さきほどはありがとうございました」
二人に向かって、丁寧に頭を下げる。
「さっき約束したしねぇ」ルイ先輩は片目でウィンクをする。
「でも結局、時間稼ぎにしかならなかったのは力不足だったな」
「そんな……。即刻、部室返上に比べたら全然ありがたいです」
そして、軽音楽部部長に向き直り頭をぺこりと下げる。
「いやいや。礼には及ばないよ。奥地も今まではあんな無茶苦茶を言い出す奴じゃなかったんだけどな。父親にアピールする実績が欲しかったんだろうけど」
現役弁護士を父親に持つ、というのはどれほどのプレッシャーなのだろう。頭に浮かべても全く想像ができない世界だ。だからといって、将棋部の降格を容認するつもりにはなれないが……。
「なんといっても、ルイが庇うとなれば僕が力にならないわけにはいかないしね」
そういって、ルイ先輩の肩の上に気軽にぽんと手を置く部長。うーむ。なるほど、二人は恋人同士だったというわけか。
「この人、細かいところ突いてくるの、ほーんとにやらしいんだよ? っ……そういえば、この間、映画見終わったときも~」
ルイ先輩が、何やら思い出し怒りをはじめそうになったので、部長は慌てて話題を変えようとする。
「ははは。それに、爺さんの金庫の件ではお世話になったしね」
「ん……え、えぇっ!?」
お爺さんの金庫、ってまさか。そういわれてみれば、面影があるといえばあるというか。なんだか、こういうのって将棋倒しのように続くもんだなぁ。
「自己紹介したことなかったっけか? 琴羽野主税。琴羽野彩の兄だよ。今後ともよろしくね、瀬田くん」
大会議室を後にして、よろよろと部室に向かう。呼吸こそ苦しくはないが、足取りはマラソン大会で走り終わった後の重さに近いものがある。
部室に着くと、がらんとした室内がいつもより暗く、広く感じた。部屋に入るとすぐ、後ろ手にドアを閉めていた。自分自身と、この将棋部に迫りくる脅威をシャットアウトしたい思いが強かったのかもしれない。
とりあえず、諸先輩方のおかげで、10月までの3ヶ月という執行猶予期間が設けられた。しかし、何も対策を講じないでいたら、秋には今度こそ降格が確定してしまうことだろう。
やはり、一人では心許ない。明日以降で美月にも相談してみよう。ドライな面が多い美月だが、とても頼りがいがある。少し、本当に少しだが、せめてこの困難にかこつけて一緒にいる時間を増やしてしまおうという下心も無いわけではない。少しだから許してほしいところだ。
泉西先生にも相談してみるべきだろうか……。非常に悩ましい問題だが、採点期間が済んだらきっと黙っていても押しかけてくるだろう。また、読心術を持っている以上、こちらがいつまでも隠し続けることも不可能だろう。よし、腹をくくって、相談しよう。
少しずつ頭の中が整理されてきた。さて、今はどうする? 今日、その二人に会える可能性は相当低いわけだが……。
「帰るか」まずは落ち着いて、現状を整理するべきだと判断する。それには、自宅の方が最適だ。
盤と駒を手に取り、片付けようとしたところ、ドアの方に人影を感じた。
一瞬、美月が戻ってきてくれたのかと期待したがそうではなかった。僕は、努めてがっかりした表情を出さないように気をつけた。
「あ、琴羽野さん」
「お久し振り」
奇遇なことに、現れたのはつい先程会った先輩の妹である琴羽野彩さんだった。彼女は1年2組、クラスは違うが、以前彼女のお爺さんの金庫の暗証番号を推理したときから知り合いになった。
アヒル口というのか、猫口というのか、口角が上がった表情であることに今日なんとなく気づいた。女の子と話をするのに慣れ、観察する余裕がでてきたためか、それとも、顔なじみになり琴羽野さんが心を許してくれたためなのか。美少女というほどではないのだが、愛嬌がある顔や仕草の持ち主である。
「お兄ちゃんから聞いたよ。なんだか、部活が大変なことになってるって……」
「え、あー……。うん」
情報が早いな、と驚く。高校生くらいになると、学校で兄弟姉妹と一緒に話すのはなかなか気恥ずかしいと聞くのだけど。メールなどでやりとりしてたのだろうか。この分だと、勝田くんもこの件を知っていたりするかもしれない。
将棋部関連の話がくると思い込んでいたが、そうではなかった。
「こんな時に相談なんて迷惑だとは思ってるんだけど……これ」
そういうと、カバンから静かに封筒を取り出し始める。
心臓が一瞬、きゅう……と締め付けられたようになる。
二人きりの時、女の子から渡される紙封筒といったら。
ラブレター……じゃないのか?
僕は、ぼーっとする頭で紙封筒を受け取った。
「開いてみて?」
「う……うん」
こういうのって、普通渡したら恥ずかしそうにしてサーッて帰っていくものじゃないのだろうか? 目の前で読ませるとは、琴羽野さんの度胸は見かけによらず強烈なようだ。いや、この展開は、逆に僕のほうが恥ずかしくないか? 琴羽野さんは僕が読み始めるのを、散歩をせがむ犬のように見つめている。
ううむ……、ここで変に抗うわけにもいかない。
封筒には特にシールや糊付けはされていなかった。おや、と少し違和感を持った。まぁ、最初からその場で開けてもらうつもりだったなら、逆にそういう加工は煩雑と判断したのかもしれないなと思い直す。
言われるとおりに、封筒を開いてみると……。
「ん!? な、何これ?」
中から出てきたのは少しサビの浮き始めた長方形の金属板だった。幅は手のひらくらいで、長さは5cmくらいだろうか。表面には凹凸がバラバラに穿たれている。
切断面や金属板の質からして、市販の製品というよりは素人が加工したもののような印象だ。
視線を上げると、琴羽野さんがカバンから似たような封筒を何枚も取り出しているのが見えた。
「全部で8枚あるの。これ、あの金庫から出てきた通帳とか印鑑とかに混じって入っていたの。他にも、歯の少ない櫛とか、ヒビの入った手鏡とか、ゼンマイ仕掛けの車とか、価値があるのか良く分からない思い出の品っぽいものはあったんだけど……」
確かに、金庫に入っていたラインナップの中では、ずば抜けて意味不明な一品といえそうだ。せめて、説明文とか添えられていればよかったのだろうけど。逝くときがあらかじめ分かるニンゲンは限られているだろう。確か、琴羽野さんは病床に臥せっている期間があったはずだったが……。そういった準備をしてしまうと、身体が死を受け入れてしまうと考えて敢えて避けたのかもしれない。
8枚全てを一枚一枚丁寧に観察してみた。長さや、凹凸の具合はバラバラのように見える。物差しで計ってみたら、横幅は12cm、長さは一番短いもので6.4cm、一番長いもので25.6cmあった。
「おじいさんって、何かものづくりをする趣味とかあったの?」
琴羽野さんはかぶりを振る。家にはそういうことができる工具さえないという。
「あ、でも戦後の一時期、板金工場で働いていたことがあった、って話をしてくれたような気がする……かも」
「戦後……かぁ」
それは随分と昔の話だ。戦後であれば、軍事機密的なものではなさそうだ。我ながら、妙なところで安堵してしまう。
「今回のはね、全然急ぎじゃないの。だから、将棋部が落ち着いてからでもいいから、この金属板がなんなのか、考えてみてもらいたいの」
今、いくつも頭を悩ませることが積み重なり始めていることは事実だ。とはいえ、人の助けを無碍に拒むほどはまだ追い詰められてはいないと思っている。
――優れたアイディアも、全て既存の組み合わせにすぎない――
何かの拍子に聞いたことのある言葉だ。消しゴム付きの鉛筆も、カツカレーも、最新の電化製品でも。元をたどると、小さな足し算の合計といえる。
物質的なもの以外――学問、技術、芸術といったもの――もきっとそうだろう。事実、春先に僕が様々な問題を解いていったときもそうだった。
僕が了承すると、琴羽野さんは嬉しそうに笑った。うん、女の子の笑顔はいいな、癒される。って、別に誰かさんを非難してるわけじゃないですけどっ!
とりあえず、一枚一枚を携帯端末のカメラで撮影していくことにした。大きさにも意味あるかもしれないので、画像の縮尺が一定になるように気をつけた。
古ぼけて価値がなさそうに見えるとはいえ、少なくとも、この世に2つとなさそうなものだ。預かるわけにはいかない。実物は持ち帰ってもらうことにした。
さて、一体これはなんなのだろう。謎が解ける日はやってくるのだろうか。
「そういえば、瀬田くん、〈ラフテイカー〉って知ってる? 孤独に泣いている子供のすぐ傍にすうっと現われて、笑顔にさせてしまうすごいヤツみたいなんだけど……」
依頼が引き受けてもらえたことで安堵したのか、琴羽野さんは他愛のない話を繰り出してくる。
無邪気な笑顔を浮かべる琴羽野さんに僕も付き合いの笑顔を向けてはいるものの、内心ではこの件を含めた大小のはてなマークがぐるぐると旋回していて落ち着かない気持ちだった。
時間制限がないことは随分と気楽ではある。焦らず焦らず。家に帰って、腹を満たして、風呂でくつろいで、将棋部の対策と一緒に少し考え始めてみることにしよう。
琴羽野さんと別れの挨拶を済ませ、備品を片付けて、僕は家路を急ぐことにした。
途中、歌を歌いながらバスに乗り込む小さな園児達とすれ違った。
「「ちーさなもりのまんなかにー、おーきなきがありましたー♪」」
一瞬、ドキッとしてしまった。随分と懐かしい童謡だ。この童謡を聴いて動揺してしまうのは、幼稚園時代の初恋の相手、ナナちゃんのことを思い出してしまうからだろう。
――人やお花や動物が、森にやってくる前から。
小さい頃に繰り返し聞かされるためか、久し振りのはずなのにすらすらと続きが頭に再生された。他にも、「赤とんぼ」や「しゃぼん玉」などもすぐに再生できる。
もしかして、幼少時代に効率の良い詰め込み教育――例えば、歌や語呂合わせで憶えるとか――をすれば、より優秀な学生が増えるんじゃないだろうか。勉強が面白くない、という学生が多いこと自体、教育カリキュラムの失敗といえないか。
あ、でも、優秀な学生が増えたら相対的に今以上に頑張りが必要になってしまうかもしれないな。うーん、悩ましいな。
あれ、僕、何で悩んでいたんだっけ……。まぁ、そのうち思い出すだろう。
家に着くと、ツンとすっぱい匂いがした。これは!
靴を脱ぎ、廊下を足早に進み、台所に顔を出す。
「もしかして今日寿司?」
「そうよー」母は手に団扇を持ち、手許の酢飯を仰いでいた。
寿司は大好物だ。え? カレーが大好物じゃなかったかって? カレーも好きだよ。でも、寿司も好きなんだよ。別にいいじゃん。
僕の帰宅に気づき、父も台所に現れる。
「砂漠じゃないが、捌くか……」
ボソッとくだらない父ギャグを呟くと、冷蔵庫から切り身をいくつか取り出し始める。
普段、料理など絶対にしない男だが、魚をさばくときだけは必ず登場する。しかし、その腕前はただのサラリーマンとは思えないほどのものを持っている。以前、薄切りにされていた透明のものがマグロの赤身だと気づかなかったときがある。
昔は荒れ狂う海原を駆け巡っていた、などと折に触れて本人は嘯いているが、腕の細さを見る限り真偽の程は明らかに偽だろう。
「今日何かいいことでもあったの?」
「……」父は答えず、無言でイカをさばいている。
「お父さん、ヘッドハンティングされたらしいのよ」母が小さく耳元で教えてくれた。
母曰く、業界内で新進気鋭の企業幹部から直々に声が掛かったらしい。入社して16年。大博打をせず、人が避けるような仕事も引き受け、堅実に堅実に生きてきた男だ。それがついに報われたわけだから、嬉しくないはずはない。
日中に連絡を受けて、夕食は寿司にすることにしたのだという。
心なしか、なで肩で猫背気味の父の背中が今日は自信にみなぎっている感じさえする。
「桂夜は海苔とか皿とか小物の準備をしておいて」
「はいよ」
寿司の準備は基本的に酢飯の準備が一番時間が掛かる。父も手際よく捌いたので、その後あっという間に夕食開始となった。
僕は早速、海苔を手に取り手巻き寿司を作り始める。四角い海苔の上に酢飯を薄く延ばす。飯をたくさん盛りすぎるとそれだけで満腹になってしまう。ネタは単純な数だけでなく、組合せでも随分味の印象が変わるからできるだけたくさん味わうには『飯は少なく』が鉄則だ。
ではまずはさっぱりとしたこの白身の魚から。これはマダイかな? エンガワやトロは美味いが最初に食べると膨満感が早く訪れてしまう。
……はぐっ。
「う、うまい……」
程よい噛み応えと舌触り。青ジソとわさびが、微妙なアクセントを与えてくれている。
ふと父の方を見ると。
寿司を醤油皿に思い切り押し付けてから、あんぐりとかぶりついている。
「父さん、醤油つけすぎだろ……」
「……」
味噌汁も麺つゆもそうだが、父はとにかく『味が濃い』のが好きだ。今でこそ問題ないが、高血圧になるのは遠い未来の話ではなさそうな気がする。ありがたいことに、僕には遺伝していない性質だ。
「問題ないわよ。生命保険それなりの額かけてあるから」
長年連れ添っている母は既に諦めモードというか、特殊フィルターが掛かっているようだ。
よく見ると、母は母で刺身だけをひたすら食べ続けている。こらっ、それじゃネタが速攻なくなっちゃうだろ! まぁ、母は納豆が食べられないので、最終的には納豆巻きを大量生産するつもりだから大問題ではないが。
本当にマイペースだな我が家は。
自室に戻って、携帯端末を開いた。そして、先程撮影した、金属板を眺めていく。思いのほか、凹凸は綺麗に撮影できていて安心した。
まだ何も浮かんでこないが、凹凸の具合や大きさからいくらかの分析ができた。

一番小さいパターンDを1とすると、長さは1から4までの4種類あった。
また、2枚ある金属板を〈パターンA〉とすると、それに一部しか異ならない〈パターンA’〉、Aの3分の4と完全に一致する〈パターンA-〉、Aの残り4分の1と似ている〈パターンD〉になっていた。残る3種類は共通点が特に無かったので、それぞれ〈パターンB〉、〈パターンC〉、〈パターンE〉と呼ぶことにした。
〈パターンE〉は唯一凹凸が一列だけに固まっていた。
寝る時間まではまだ少し時間がある。今日は宿題も特に無いし、少し考えてみるようか。金属板と凹凸……、金属板と凹凸……、
金属板 + 凸凹 = おろし金?
いやいや、板の厚さや凹凸の少なさから考えてもそれはなさそうだ。
とすると。
金属板 + 凸凹 = 点字?
少しありえるかもと思ったが、やはり点字にするには凹凸が少なすぎるようだ。
前回とは違い、これはなかなか手強そうだ。何か、ヒントは無いかなと部屋の中の本棚を物色してみる。すると、奥底から懐かしい雑誌やマンガが発掘された。
しかし、それは呪われた発掘物だった。気づけば僕は、寝るまでの時間をその発掘物の閲覧に費やしてしまっていた。
小説『Spring in the Spring =跳躍の春=』(5/5)
*****
明日の答えなら 今日のどこかにしかない。
*****
第五章 『金曜日』
翌日の放課後。仮入部の最終日。僕は賑わう音楽室でなく、寂れた将棋部の教室の椅子に一人ぽつんと腰掛けていた。
(これで……いいんだよな)
丸一日考えて出した結論だったが、まだ僅かな心残りがあることは否定できない。
軽音楽部は確かに楽しそうだった。しかし、もやもやした気持ちでいる僕がその集団の中で悪影響を与えないだろうか、上達せずにメンバーの足をひっぱってしまうのは心苦しい。
将棋は元々孤独な競技だ。ゴルフやボクシングと違い、試合中に誰の助言も受けることはできない。運の要素もなく、〈負け=自分の判断ミス〉という厳しい現実を突きつけられる。
しかし。
孤独な競技ゆえに、自分のことは自分の責任で収められる。他人に迷惑を掛けることはない。迷った僕が何かやっとけそうなことはといえば、駒を持つことだと考えた。
ただ、最後に決め手となったのは美月の言葉だった。
――――ケーヤの中で将棋はなくなってなかった
美月は平気で嘘をつくタイプではない。いくら〈通し〉の最中とはいえ、その言葉が偽りの文字列であったとは思えなかった。
将棋部は恐らく、将棋のできない顧問――泉西先生と僕の二人だけになる。あの訳の分からない教師と3年間一緒か……。今から卒業写真の部活のページが非常に心配だ。同窓会の度にネタにされたりしないだろうかと気が気ではない。
一人だけだが、高校の大会も個人戦だけなら参加もできるはずだ。最近ではPC用ソフトも強くなってきているから、日々の対戦相手には不自由しない。学校に余っているPCが無いか泉西先生に相談してみるか。あれだけのことを言ってたのだから、少しは協力を要請しても問題は無いはずだ。
よし……。当面の目標は立った。高校生でナンバーワンを目指すかな。
僕が早くも来週からの活動を企てていると、
「あれ。今日もいる」
後ろから急に声を掛けられてビックリする。それは、ヤツの声ではなかった。
「み、美月?」
「何、驚いてんの?」
美月は眉根を寄せて訝んでいる。
「仮入部、最終日だぞ……。まさか、美月も将棋部入るつもりか?」
「つもり……って、もう入部届は出し終えたけど?」
美月が、将棋部に、本入部?
俄かにはとても信じられない。昨日、僕を江辻の前に連れて行ったことで、美月が将棋部に近づく理由はもうないと思っていたのだから。
同じ高校に通っているはずなのに、なんとなく、もう二度と会えないような気がしていたのに。
僕の言いたいことが伝わったのか、美月は自分から話し始める。
「顧問のセンセが『好きな時にくればいいから』って言ってくれたから。あたし、放課後はなるべく自由に過ごしたいし。先輩が居ないのも気楽でいいしね」
なるほど。一応、納得できる回答ではあったが。「ケーヤがいるから」という理由じゃなかったのは残念至極だ。さすがにそれは夢見すぎだったか。
「ところで、軽音部の本入部届はもう出してきたの?」
現実の厳しさを突きつけられたばかりの僕に、美月はそんなことを言ってきた。意味がよくわからない。
「俺も将棋部に本入部したから、さっきわざわざ美月『も』って言ったんだけどね」
しかし、美月はさらに続けた。
「あ、そう。『掛け持ち』はしないんだ」
「えっ?」
鳩がまさかの豆型スタンガンを食らったような表情を僕は浮かべていたかもしれない。
「知らなかったの? 部活は掛け持ち可能だよ。生徒手帳に書いてあるでしょ。とりあえず、ケーヤもすればいいのに」
「ケーヤも……って美月は将棋部とどこなんだよ」
「帰宅部」
「あのさ。そういうのを幽霊部員っていうんだ」
……さてと。
ここにきて、部活動の掛け持ち自体は可能だと知ったのは大きいが、果たして有効に実現可能なことなのだろうか。
つまり、将棋で高校生全国一を目指しつつ、音楽も精力的に活動するってことだ。
ギターだって、まだCとGとAmのコードしか押さえられない僕が、将棋の片手間にできるほど楽な世界ではないはずだ。
将棋だって、3年のブランクがある。小中ではまだ覚醒していなかった、あるいは、急成長を遂げた猛者がきっとひしめいているに違いない。一筋縄ではいかないだろう。音楽の片手間では通用しないのではないだろうか。
昔から、〈二兎追うものは一兎も得ず〉というじゃないか。そんな、異次元のような活動ができるわけが……。
――桂だけは……次元を超えられる……――
頭に、そんなフレーズがフラッシュバックした。
それは。
(なんだよ……自分で言ったセリフじゃないか!)
僕は、高速で自分自身の高校生活をできるだけ深く、そしてリアルに読んでいく。それは、随分と深くまで及んだ。
人間には死の直前に人生の走馬灯というものがあるというが、それを未来に対してしている感覚に近かった。第三者的に見たら、非常に危ない人間かもしれない。
そして結果が出る。
「……よしっ」
急いで読んだから、読み間違いかもしれない。でも、ここで立ち止まっていては、また時間切れのブザーが鳴り響き、後悔の3年間を送ってしまうことになるかもしれない。
(迷ったら、何かやっとけ、だよな!!)
僕は美月の方を正面に見据えて、「……悪い。しばらくここ頼む。軽音行ってくるから! ……と、もう一つ」
そして、今、取り急ぎ言っておきたいことが。
ビシィッッッッ……!!
僕は、手許にあった玉将を力強く叩きつけ、真剣な顔で宣言する。
「俺、王将も好きだけど、玉将はもっと好きだ!」
突然、脈絡の無く謎の宣言をした僕に、さすがの美月も理解が追いついていない様子だ。
いや、分からなくていい。むしろ、その方が堂々と言えて都合がいいといえるかもしれない。
相手が意味を理解していないから恥ずかしさがなく、しかし、自分は達成感を得られている。
今日のところは、これで十分。3年間のうちに、正式な機会が作ればいいさ。そんな風に、余裕に構えていたら。
「おー、下僕……もとい、部員たちよ、集まっとるな」
ヤツだ。
(……って、このタイミングではヤバい!)
慌てて、退散しようと思ったが、間に合わず。そして、
「どうした瀬田。『玉将の点が美月の笑窪を表現したことをばらされたらまずい!』ってな表情してるが?」
「……~~っ」
恥ずかしさで、全身、特に顔が熱くなっていくのを感じた。後ろからは、何故か風を切る鋭い音が聞こえる。ゆっくり振り返ると。
(その音かよ!)
「……そんなに、あたしの笑窪が拝みたいなら、デコピン二発でどう?」
美月が、眉根を僅かに寄せつつ、物凄い素振りをしていた。
しかし、先日のように不快な表情を浮かべるでもなく、軽妙に切り返しを見せたということは、美月に僕が伝えたかった笑顔の魅力がいくらかは伝わったと言うことではないだろうか。
それなら、恥ずかしい想いをしても損はない。あの強烈なデコピンは御免こうむるが。
「と、とにかく。軽音楽部に届出してくる!」
僕は、逃げるように将棋部の部室を飛び出した。
後方の教室からは、何故か、泉西先生の「っ痛えっっっっ!!」という悲鳴が響いてきた。
早速、さっきの〈読み〉が大きく脱線した僕の高校生活だが、どうやら、つまらないまま終わることだけはなさそうだ。
無事、軽音楽部にも本入部届を出し終えて、来週の火曜日には早速ギター講座にも参加することにした。
紆余曲折あったが、とにもかくにも僕の高校生活の駒はこれで全て整い、今まさに3年間に亘る一局がはじまろうとしている。
すぐにでも第一手目を指したい、はやる気持ちを抑えて、静かに考える。
瀬田桂夜の生き方のルールは、瀬田桂夜が決めることができるのだから。既存の考え方や、枠にとらわれることなんて無いはずだ。
季節は春。春はspringであり、springは〈跳躍〉でもある。まさに〈桂〉のためにある季節といえるかもしれない。
だから、もっと素直に。もっと自由に。こんなことだって、できるはずだ。
僕は頭の中に将棋盤を浮かべると、勢い良く駒を打ち付ける。
初手、5五桂――。

小説『Spring in the Spring =跳躍の春=』(4/5)
*****
負ければ悔しくて、もう一局。
勝てればうれしくて、もう一局。
それがこのゲームの怖くて素晴らしいところ。
*****
第四章 『木曜日』
翌朝のホームルーム前、福路くんが1組を尋ねてきた。
「昨日は本当に助かったよ。あの後、『字間違えててごめん……』って謝ったら、ちゃんと許してもらえて」
額を指差して、「穏便にね」と付け加える。
左様ですか。そいつは、めでたいことで……。
「あ、そうだ。もし知っていたらでいいんだけど……」
確か、福路くんは僕と別の中学出身だ。そこで、念のため聞いてみたいことがあった。
「『織賀美月』って女子生徒、知ってる?」
「え? あの可愛い一年女子ですよね。運動神経も頭も抜群、才色兼備の天才ってところですけど、あんまりに無表情だから何考えているか分からず絡みづらいという評判ですが。それがどうかしました?」
「ああ、いや、なんでもないよ」
「入学早々、告白仕掛けて玉砕して、人目をはばからず涙を流した男子生徒が数名いるとかいないとか。残念ながら、〈ラフテイカー(笑顔受取人)〉が来てくれる年齢でもないのですしね」
「ラフ……テイカー? 南の方の食べ物……だったっけ?」
「それは、ラフテーです! 噂はご存じないですか。
孤独に泣いている子供のすぐ傍にすうっと現われて、笑顔にさせてしまうすごいヤツなんですが、その正体というのが……」
そのとき、ホームルームの開始を告げるチャイムが鳴り響き、僕と福路くんは慌ててそれぞれの教室へ戻ることとなった。
話も脱線指定しまい、結局のところ持ち得ている情報以上の収穫は得られなかったのだった。
*****
朝の福路くんとの会話以来、僕は授業中を含めて一日中考え続けていた。
美月が、なぜ将棋部に足を運び続けているのかということをだ。
ここ数日、レクチャーを通してみた感想は『天才』だった。福路くんも評していたがそれに異論はない。
一見、整った容姿の方に注目してしまいそうだが、異質なのはその処理能力だったのだ。
一度理解したことをすぐに自分のものとして、正確無比に扱う。まるで、プログラムやコンピュータのようだ。
そこで浮かぶのは、棋界を騒がせている冷谷山三冠のことだった。
25歳でプロとなって以来、現在進行形で将棋界の記録を更新し続けている30歳の男だ。
同業のプロ棋士からも「なぜプロ棋士になったのか」「他の分野であればもっと別の偉業を成していたのでは」と言わしめる天才だ。
「天才は異質なものだ」冷谷山本人は何かのインタビューでそう言っていたそうだ。
異質――つまり、凡人には天才は理解できない、ということならばそれ以上の探求は不可能ということになる。
(結局は、考えるだけ無駄なのかな)
僕はシャープペンシルを指先でクルクルと回しながら、5時間目の授業の終業時刻の到来を待ち望んでいた。
そしていよいよ放課後。緊張しつつ部屋で待つと、美月は現れてくれた。そして、こちらが声を上げるより早く、
「今日は、ちょっと付き合ってほしいところがあるんだ」
と切り出してきた。口調は昨日の『笑窪事件』以前のものと変わりがない。しこりが残らなかったことにひとまず安堵しつつ、「付き合ってほしい」という言葉につい敏感に反応してしまう。さすがに、デートの誘い……というわけでもなさそうだが。
「別にいいけど?」
そっけない感じを装っているが、心臓は高鳴ってきている。
「それなら、片付け片付け」
美月に促され、将棋盤と駒を片付けて、校舎を後にした。
向かった先は、駅の近くの繁華街だ。この辺りは、飲食店や本屋など様々な商店が立ち並んでいる。
美月はそのうち、〈哲笠ビル〉と銘打たれている建物の前で立ちどまる。1階が喫茶店になっているようだ。
(喫茶店で何か食べたいものがあるとか?)
男と二人じゃないと食べられないものとは、果たしてなんだろうか。牛丼とか、串揚げみたいなゴツい食べ物ならありえるかもしれないが、喫茶店のメニューにそういう類のものなんかあるだろうか。
二人分の量の甘味を食べたいが、一人で注文すると人目が気になるから、僕に一旦注文させようとでも言うことだったりして。
しかし、僕の予想をあざ笑うように、美月は1階の喫茶店には入らず、近くにあったエレベータで5階のボタンを押して待っている。
5階のプレートには〈(株)レンタルルームサービス〉なる文字が書いてある。なんとも分かり易い会社である。
貸し部屋でいったい何をするつもりか、という問いの答えは一切見当がついていない。
エレベータを降り、居室の中をなおも進むと〈Cルーム〉と書かれたドアが見えてくる。その前で美月は立ち止まり、「ここ」と指さして待っている。
ドアに何か張り紙があるわけでもなく、鉄の扉の先は見えない状況だ。全く想像がつかない。
しかし、ここで突っ立っているわけにもいかない。
僕は意を決して、ドアを開いた。
*****
ドアを開くと、椅子に白髪の人物が座っているのが見えた。入口に立っている僕に声が掛けられる。
「ようこそ。どうぞ、こちらに……」
前髪を垂らし、サングラスを掛けているが、肌の具合やその声から同い年くらいであることが分かった。
白髪に見えたが、髪はブリーチしているのだろうか。白髪と銀髪の違いは僕にはよくわからない。
一歩一歩近づく。
すると、口許の印象や、彼の手前に置かれているものがよく見えてきたことで僕の推理は100%に到達する。
「お前……江辻か?」
「ごぶさたしていますね。瀬田くん」
満足気な声で江辻が応じる。後ろを振り返ると、美月が相変らず無表情な顔で立っている。
「謀ったのか?」などと失礼なことは聞かない。僕が自分の意思で付いて来たことに違いはないのだから。
ただ、これだけは確認しておきたかった。
「美月、君に何のメリットがあったんだ?」
江辻と美月の間にどんな関係があるのか。恋人同士だというならば、瀬田桂夜としては残念だけど、まあ妥当な理由と言える。
ただ、脅迫されているような事実があったなら、それは見過ごすことはできない。
「今は、言えない」
数日の付き合いではあったが、美月のことは少しは分かってきているつもりだ。
『言えない』のではなく『今は言えない』理由なら、まだ今の自分を納得させられる。
数日間を含めて要するに、江辻は美月を通して、僕を呼び寄せた。そういうことだ。
美月が僕に近づいたのも、僕と親しくなり、事を進めやすくするためだった、ということだろう。
「事情はだいたい分かった」
僕は、江辻の前に置かれている将棋盤を指差して言う。「要するに、きみとそれをすればいいんだろ?」
人質がいるわけでもない、褒賞金が出るわけでもない、僕にはメリットがない話だ。それは理解している。
しかし、ここで去れば江辻は確実に不完全燃焼だろう。江辻がそうなれば、美月も恐らくは十分な報酬を得ることはできないだろう。
そして、そんな状況を生んだ張本人という後味の悪さが、僕には残る。
だから。
早く江辻を満足させて、こんな不快な状況から脱するに限る。
部屋の奥に進み、将棋盤が近づくにつれ、駒の並びは初形ではなく差しかけのものだと分かった。
そして気付く。
「これは……っ」
何度も夢で見た。うなされたこともある。最近は、やっと見なくなったというのに。
見覚えがある局面。いや、むしろ忘れようがない局面。
*****
小学生の時、僕は将棋少年だった。将棋の駒などはいつもポケットに入れて持ち歩いており、近所では「ビスケットと駒を間違えているのでは?」という噂が立ったとか立たなかったとか。
ルールは父から教わった。勝敗によって、おやつの量が増減するという仕組みが僕の心を熱くした。半年で父と同レベルまで成長し、一年後には父では相手にならなくなって、隣町の道場にも通うようになった。
世の中は広い。通いはじめの頃は、負けることの方がずっと多かった。
それでも、子供特有の才能が伸びる時期に合致したのか、将棋というゲームとの相性が良かったのか、僕は物凄い勢いで強くなっていった。
地元の同世代ではもう勝てる者がいなくなった小学6年生のころ、全国の将棋大会に出場した。
さすがに、全国の猛者が集まるだけあって、一筋縄ではいかない戦いばかりだったが、それでも予選を全勝で突破し、ベスト4までトーナメントを勝ち上がった。
(この分なら、優勝できそうだ……)
あと2勝で全国一の座が見えてきた。
心に慢心があったかと言われれば、否定はできない。しかし、そうでなかったとしても。奴は強かった。
名前は、確か江辻隆太といった。
勝負自体は、序盤から中盤までほぼ互角だった。
しかし、終盤になり、僕の方が僅差で有利になってきた。
そして、長手順ではあるが相手の王将に詰みがありそうだと気付く。が、分岐が多く、非常に難解な手順だ。
詰めに行くときは、多くの駒を相手に渡すことになる。仮に読み間違いで詰まなかったとしたら、逆にこちらが負けとなる。ボクシングで大振りのストレートを放つようなもので、空振りしたら手痛いストレートをお見舞いされることになるわけだ。
より安全な手も勿論ある。しかし、この江辻という少年も強い。もしかしたら、一手緩めた瞬間にこちらが詰まされるおそれもありえた。
さらに、大熱戦だということでギャラリーも一層増えてくる。踏み込むべきか、安全にいくべきか……。どっちが正解なのか……。
ようやく、自分の中で方針を決めたその時。大きな落とし穴が待ち受けていたのだ。
気づいたのはギャラリーを含めた、悲鳴のような脱力したような大きなざわめき声だった。
将棋大会の対局中にそんな大声が巻き起こるとは不自然だ。誰か人でも倒れたのか、まさか目の前の江辻少年が?
そう思い正面を向くと、彼の視線は将棋盤の外に向けられているのに気づいた。その先にあるのは、アナログ式のチェスクロックだった。赤い板が垂れ下がって揺れているのは、僕が時間切れで負けたことを意味していた。
「あ……」
一瞬、頭が真っ白になった。読みに集中していて、すっかり失念していた。
ギャラリーは「あぁ……」という声を漏らしながら、一人二人と散っていく。
あとには、放心状態の僕が残された。
その当時、デジタル式のチェスクロックを子供の大会で使うことは珍しく、持ち時間を使い切ったら即負けというシビアな世界だった。
迷わず指し続けていたら勝てていたはず、何であんなに慎重になりすぎてしまったんだ。自責の言葉ばかりが頭に浮かんでくる。
結局、大会はその江辻が優勝した。それでも僕は3位決定戦を勝ち、記録上では3位の銅賞で終えることはできた。
全国3位は、傍から見たらそれでも立派な成績だったのではないかと今でこそ思う。
ただ、小学生にしてみたら、銅の色は、金色の輝きに比べたら随分とくすんだ色という印象でしかなかった。
テストの点数が振るわなかった時も、リレーで抜き去られた時も、『自分には将棋がある。将棋なら、誰にも負けない』といった心の支柱があったから、今までやってこれていた。それがその日揺らいで、そして一気に折れてしまったのだ。その日以来、僕は駒と盤を部屋の奥底にしまい、本やテレビをはじめとするありとあらゆる将棋に関連するコンテンツから遠ざかった。
(将棋なんて、ただのボードゲームだ)
(そのうち、必勝法がいくつか確立されて、それを暗記するだけのゲームになってしまうんだ)
(将棋は捨てる。将棋から離れる。将棋なんか……将棋なんか……)
大会終了後、数日の間は両親も慰めや3位という実績の礼賛をしてくれていたが、僕の〈将棋断ち〉が本気であることを感じ取ったのか、その後は家庭の話題に上がることはなくなった。
中学に入ると、当時はやっていた漫画の影響で、テニス部に入部した。練習もきつかったし、結局レギュラーになれなかったりと活躍はできなかったけれど、まあそれなりに充実した日々は過ごせた。
なにより、将棋無しでもそれなりに楽しい学生生活を過ごせたことが新たな心の支えになりつつあった。
(自分は、将棋だけじゃない。なんだって、やろうと思えばそれなりにできるんだ!)
そうして、自分の中にあった将棋の存在にそっと埃をかぶせて行った。
*****
「どうしても、あの時の続きがしたくてね」
「……」
僕が江辻に時間切れで負けた、あの準決勝の対局のものだった。
「いい性格になったんだな。おかげで、またしばらく悪夢には困らなさそうだよ」
「あなたの手番からです。今日は持ち時間は無制限で」
無制限と来たか。つまり、時間でなくて双方の実力のみであの試合の勝敗を確定させたいということだろう。
江辻は完璧主義者だ。一局しか指していないが、将棋を通してそれは理解した。無駄駒を作らず、全ての駒が何かの役割を持つように動かすその指し手がそれを物語っていた。
「……OK」
僕は引き受けた。負けたところで、失うものは特にない。ただし、たとえ勝ったところで、得るものもない。僕にとって、将棋は既に心の支えではない。なにものでもないから。
そしてこの局面で、指すべき方針も、指す手順もは既に3年前に決断していた。今はそれを再生するだけだ。ゆえに、持ち時間など、必要ない。
――パチッ………
僕が攻める。
「一つ、勘違いしないでほしい」
美月が後方から話しかけてくる。通常、対局中に話掛けてくるのはマナー違反ではあるが、どういったことを話してくるか興味があったので、制したりはしなかった。
――スッ………
江辻が金将を横にスライドさせて受ける。
「依頼には条件があった」
――ピシッ………
江辻の桂馬を銀将で取り、攻める。
「『もし、ケーヤが将棋をやめていたら連れてこなくていい』って」
――カチチッ………
江辻が銀将を取る。その手は僅かに覚束ない。
「でも、ケーヤは将棋部に居た」
――ビシッ………
盤の隅でくすぶっていた角行を中央に展開し、王手を掛ける。
「将棋部で駒をいじってた」
――パチリッ………
江辻が王将を真下に逃がす。王将は升目から僅かにはみ出ていた。
「あたしに教えてるときも辛そうに見えなかった」
(それは……。美月だったからだよ……)僕は心の中で呟く。
――ピシッ………
持ち駒の歩兵を打ち、攻める。
「念のため、3日間様子をみたけど」
――カチッ………
江辻が王将を左下に逃がす。その際に僅かに左隣の香車に触れて、香車が斜めになった。
「ケーヤの中で将棋はなくなってなかった」
(美月からは、そう見えていたのか)
当人のことは、当人にしか分からないことがほとんどだろう。しかし、当人だからこそ見えていないこともあるのかもしれない。鏡とか、写真とか、そういったものを使わないと、そもそも人間というものはは自分自身の顔さえ知ることができないのだ。
美月で言えば『笑顔の魅力』だろう。僕はそう感じていた。
僕で言えば、それは『将棋への想い』なのだろうか……。
――ピシッ………!
ひときわ大きい音で持ち駒の銀将を打つ。後は簡単な追い詰めだ。江辻ほどの実力者なら既に理解しているだろう。
勝敗は決したのだ。あの時の自分の読みが正しかったことが、3年の歳月を経て証明できた。
「だから、今日、来てもらったの」
美月の贖罪ともとれる話もちょうど終わったようだ。
「……負けました」
江辻が持ち駒に手を被せながら、頭を垂れる。それを見て、僕は静かに拳を握り締めた。
しかし、勝利に喜んだわけではなかった。頭の中にあるのはもっと別のことだ。僕は、対局中に浮かんできた疑念を確信に変えるために問いただす。
「……どうして、投了? そっちは詰まないけど?」
僕が発した言葉に、江辻は虚を突かれたようだ。
「持ち駒の桂馬でピッタリ詰むでしょう。簡単な手順です」
(そうだ。確かに、桂馬があれば詰むけどな)
「きみこそ、何を言っているんだ? 持ち駒に桂馬など持っていないけど?」
僕の不意打ちに、江辻ははじめて動揺した様子を見せた。
「7手前に、こちらの銀将と交換したでしょう」
「どうだったかな、したかもしれない。でも、その桂馬は『物理的に、今、どこにある』んだ?」
僕は両手を広げて肩をすくめてみせる。
江辻は言葉に詰まった。その様子を見て僕は確信した。
「なぁ、江辻。両眼、どうしちゃったんだよ……」
僕は、広げていた右の掌から桂馬を駒台の上に転がした。カランという音が、部屋に広がる。
この桂馬は先ほど、江辻が頭を下げて投了した後に素早く握り締めていたのだ。江辻にも美月にも分からないように。
その後、江辻を挑発した際に目の前で広げて見せていたのに、彼はそれを指摘することができなかった。それは、彼が光を失っていることの何よりの証拠だ。
「……ふぅ」
観念したのか、江辻はもう動揺していなかった。そのかわりに一つ、小さな息を漏らす。
「気づかれてしまいましたか……。実は、あの大会の直後からちょっとした病に罹り、今は全く見えていません」
「……」
恐らく、美月が対局中に不自然な話を延々と続けていたのは、僕の差し手を盲目の江辻に伝えるため、事前に取り決めをしていた〈通し〉の暗号だったのだろう。暗号のルールは全く見破れなかったが。
江辻は、静かに語り始める。
「……光を失い、最初は将棋なんてやめてやろうと自棄になったりもしました。しかし、時間が経っても、脳裏から将棋を追い出すことが一向にできませんでした。
そのうち、逆にそれが将棋だけに専念できる環境だと考えることもできると気づいたのです。
それから、毎日健常な人と同じように振舞えるような訓練を重ねました。……結局、まだまだ修行が足らなかったわけですが。気づいたら、3年が経っていました。
よほど印象に残っていたのでしょう。その間も、あの対局のあの盤面が暗闇の中には、毎日のように浮かびました」
「試合に勝って、勝負で負けた、という状況だったからだと思います。勝手な思い込みですが、この試合の顛末をきっちりと終わらせないと、私の第二の人生は始まらないと思ったのです」
「それなら、今日が第二の人生のスタートだな」
「ありがとうございます。次にお会いする時は、今の私と勝負をしてもらいますよ」
「……ん。ああ」
あいまいに答えたが、あいにく僕のほうには明日からも将棋をするつもりは全くなかった。
将棋への歪んだ偏見。将棋の未来に僕が感じた閉塞感。それをここで語るのは容易い。
しかし、江辻の将棋への情熱は本物だ。光を失った後は、それを基軸にして今日も生きているようだ。
そんな人間に、僕の思いをぶつけるのはさすがにためらわれた。
「ともかく、これで全部終わったはず。……俺は、学校に戻る。まだ部活動の時間が残ってるから」
江辻は小さくゆっくりと頷いた。特に不満はなさそうだ。
そして、美月は。相変わらず無表情な顔をしているが、部屋を出て行くことに異論はなさそうだ。
ドアを閉める直前、最後にもう一度だけその姿をじっと見た。
(『瀬田桂夜』じゃなくて、『江辻の依頼した人物』に用があったんだよな)
自分が普通に生きていたのでは、話をするきっかけさえなかったであろう同い年の美少女。
数日間のやりとりも、果たして、幸だったのか不幸だったのか。今はまだ判断が下せるほど心は冷静ではなかった。
僕は、くすぶりはじめた想いを振り払うようにして、〈Cルーム〉を後にした。
*****
僕は、校舎に戻ってきた。部活動の時間は残り30分程度だ。勿論、軽音楽部の枠は開いていないだろう。
しかし、顔を売っておけば、もしかしたら明日の最終日に潜り込めるチャンスが生まれるかもしれない。
そんな淡い期待で音楽室を訪れた。
例の「本日満員御礼 またきてね~♪」の張り紙はなかった。軽快な音楽に誘われるようにして、ドアを静かに開ける。
入り口から中を覗いてみると、ギター、キーボード、ドラム、パーカッション。様々な楽器から、様々な音色が生まれて溢れ返っている。
これこそ、僕の思い描いていた高校生活だ。
「キミ、仮入部希望の子?」
「あ、はい……」
僕の存在に気付いた男の先輩が話しかけてきてくれた。
「ちょうど、さっき早退しちゃった子がいるから、寄ってく? 今からだと30分もないけど」
「えっ、あっ、はい! ぜひ!」
その早退した子には悪いが、幸運としか言いようがない。僕は4日目にしてついに、音楽室のドアを越えることができた。
「楽器は個人のを持ち込んでもいいし、備品を使ってもオーケー。ピアノは確実に順番待ちになるね。中にはジャズとかやる連中もいるので、吹奏楽部とかも交流があるよ」
先輩は、あれこれ指差しながら部活動の説明を丁寧にしてくれる。
「キミ、楽器は何かしてる?」
「えーと、ギターやりたいんですけど……まだ独学ではじめたばかりで」
「なるほどね、ギターは上手い奴が一人いて定期的に講座を開いているみたいだから、習うとあっというまに上達すると思うよ」
想像以上に、素敵な部活動じゃないか……。きっと、顧問の先生もまともに違いない。
もう決めた。僕はこの部活動に骨をうずめるぞと心に決める。本当にうずめてしまったら、事件になってしまうので、あくまでも比喩だ。
辺りをしげしげと眺めていたが、ふと、不可解な光景を眼にした。
「……曲がりくねったみーちー♪」
可愛らしい女の子の歌声とピアノやドラムの音が聞こえるのに、音楽の聞こえる方向には楽器を弾いている男子生徒が一人しかいないのだ。
「……!?」
じっと見ていると、男子生徒が近くにあったパソコンのキーを軽く叩く。すると、音楽も鳴り止んだ。
(なんだ、録音か)
これは、メンバーが集まらないときや、一人で繰り返し練習するには非常に重宝しそうだ。音楽も進化しているのだなと感じる。僕なんかはギターの初心者も初心者なので、最初のうちはこうして練習をするのが迷惑にならなくてよいかもしれない。
僕の視線に気付いたのか、先輩が説明をしてくれた。
「ああ、あれね。高楠くんがやっているのはDTMっていうんだ」
「ディーティーエム、ですか?」
「そう。デスクトップミュージック。あらかじめ、インプットしておいたとおりに、コンピュータで曲を演奏させることができるんだよ」
「は、はぁ……」
「そうだなぁ。例えば、ギター音を7音以上同時に出したり、とてつもなく速くて細かい動きも毎回完璧に演奏できたりも自由自在だよ」
最初は、録音とどう違うのか、何がメリットなのか、図りかねていた僕にもだいぶ理解できてきた。これはなかなか便利そうだ。
「つまり、ボーカル以外はコンピュータって演奏させたりできるってことですね」
「お? いやいや、あのボーカルもコンピュータだよ。今はだいぶ種類も増えて、老若男女色々あるんだよ」
「えっ、ボーカルもですか」
僕は驚く。あれだけ滑らかに歌っていたのに……。確か、パソコンに付属しているようなテキストリーダーはもっとカタコトな話し方だった気がするけれど。音楽用は特別なのだろうか。
「それだけじゃない。実は、作詞作曲編曲、今はこういったものも全部コンピュータで自動生成できるんだよ。和声法とか対位法って知ってる?」
「い、いえ……。すみません」
「えーと、まあ簡単に言うと、人間が『あ、いいな』って思える曲って、ある程度は法則化できるんだ。それをコンピュータでランダムに組み合わせたりすると、曲自体は簡単にできるんだ。詞もアレンジも同じ要領だね」
突然の話に、なかなか頭が追いつかない。便利そうで、いいなとは思うんだけど。それって、つまりは。
僕は膨れ上がってきた疑問を先輩に投げかけてみる。
「でもそんなのがあったら、音楽やってる人たちみんな困らないですか? 新曲もコンピュータで作れて、完璧で凄い演奏もコンピュータでできちゃうなら、みんな、何を音楽に求めるんでしょうか?」
決して、困らせるつもりで言ったわけじゃない。
でも、先輩は僕の問いにすぐ答えられなかった。
「……実は、さっき早退しちゃった子も同じような反応でね。最近、音楽CDが全然売れないのは知ってるよね。ミリオンヒットはいまや過去の話、音楽番組も視聴率を取れない。……今じゃ、音楽というものがゆっくりと衰退してるのかもしれないね」
「そんな……」
そんなことないですよね、と言いかけたが、言葉を続けることができなかった。
*****
その後、僕は部活動終了時間まで音楽室に入り浸っていた。結局、念願の仮入部は果たせ、過ごすこともできたものの、頭の中はすっきり晴れない状態だ。
近くの窓から、眼下を見下ろすと生徒が徐々に下校していく様子が見えた。
彼らは身体は疲れているはずだが、充実した表情を浮かべて楽しそうに見えた。楽しそうに見えるのは、一体何故だろう。
(将棋も斜陽、音楽も衰退……か)
楽しみにしていた高校生活がついに始まったかと思っていただけに、一層大きく感じられる閉塞感が僕を包みこんでしまったようだ。
(一体、どうしたらいいのか。見当もつかないや……)
夕陽が廊下に一筋の影を作った。視線を向ける。
それは、よく知った人物――泉西先生だった。
てっきり、「将棋部来ないで、軽音楽部に行ってたのか!」などと言われるのかと覚悟していたのだが、そうではなかった。
「どうした瀬田、元気ないようだが」
声色も普段と違っているように感じる。
(みりゃわかるでしょ。でも泉西先生には僕の悩みなんてわかりっこないさ)
「『みりゃわかるでしょ。でも泉西先生には僕の悩みなんてわかりっこないさ』って言わんばかりの顔だな。ってこら! お前、俺さまを相当見下してやがるなっ!?」
思っていたことを一字一句ぴたりと言い当てられて、僕は驚愕する。まさか、読心術というやつだろうか。
「『読心術』っちゃあ、『読心術』かもな。現国教師の力をなめるなよ。ちなみに、いい女性になかなか巡り合えず『独身術』もしっかり身につけてるがな。……って、余計なことしゃべらせるな!」
「勝手にしゃべってんじゃないすか!」
普段と違っているかと感じたが、どうやら思い違いだったようだ。
はっはっは……と泉西先生はしばらく笑っていたが、急に真面目な顔になり、僕に向き直る。
「迷ったら、何かやっとけ、だ」
「え?」
「信じるかどうかはお前に任せる。昔話&独り言だ。
学生時代の俺は、この『読心術』っぽい能力のせいもあって、周りから必要以上に避けられていたな。『泉西に近づくと、秘密が覗かれるぞ!』ってな。落ち込んでいた俺に、担任の先生だけがこう言ってくれたよ。『君の力は実にすばらしい。将来は、その力できっと多くの人が救われることだろう』
嬉しかったな。必要とされるってのは悪くねぇもんだ。この力を活かしつつ、できなかった楽しい学生生活をもう一度やり直したい、と思ったらスクールカウンセラーしかないと思ったんだ。目標ができたからな、勉強したよ。したけどさ、ダメだった。暗記物はさっぱりだった。
気付けば、俺は動物園のペンギンの世話をしていた。北国の冬は寒かったが、ペンギンたちは可愛かったよ。楽しかったが、散歩中のペンギンに大脱走されて大渋滞を起こして、大目玉を食らってあっさりクビになったよ。ペンギンの心は全く読めなかったな。
手っ取り早く稼ごうと思って、雀荘に入り浸ったらこれが予想通り大儲かりでな。儲かりすぎて、目をつけられて、跡もつけられて、海に沈められかけて。
で、気づいたら、この高校で教師をしてた、というわけだ!」
「……ぶっ飛びすぎでしょう」
「まあとにかく、だ。こうやって、お前と話ができてるってことは、俺の昔の夢が一つ叶いかけてるってことだろ? どうしようもないことばっかだったけど、立ち止まったり、何もしなかったりしなかったのが良かったんだと思ってるぜ。……こう見えても、うれしさのあまり、俺の中では盛大にお祭りが開催されております」
「は、はぁ……」
気付けば、辺りは既に暗くなり、屋外では街灯が灯りつつある。
「と、まあいろいろ言ったが。何かしてなきゃ何も変わらんもんだ。状況が勝手に変わることはめちゃレアだ。良い方向に変えたければなおさらだな。だから、何かやっとけ。学生時代は長いようで短いぞ!」
最後にそれだけ言うと、泉西先生は踵を返し薄暗い廊下に消えていった。
(何かしないと何も変わらん……か)
状況が芳しくなくても、何もしないままだと事態は一向に良い方向に向かわない。その考えは奇しくもパスの許されない将棋も同じだ。
明日の僕は、どんな決断を下すのだろうか。
小説『Spring in the Spring =跳躍の春=』(5/5)に続く
小説『Spring in the Spring =跳躍の春=』(3/5)
*****
一日は短い 悩むにはもったいないから
今日もベストの自分をイメージして走ろう!
*****
第三章 『水曜日』
翌朝、僕は始業前に2組の琴羽野さんを訪ねた。なんだか気恥ずかしいので、昨日と同じ別館の廊下にばらばらに移動してから、話を始めることにした。
「あれから、どうだった?」
まずは、そこから。既に解決済みであれば、僕の出番は不要だ。
「全然ダメ。年月日じゃなくて、歩数とか戦場とかでも色々と調べてみたんだけど、歴史研究家じゃないから詳しくもないし……」
「そもそも、おじいさん、歴史好きだったの?」
「えっ!? えーと、いやそういうのは、あんまりなかったかなぁ……」
「あと、暗証番号って、自分で設定できるものなのかな」
「それはできるみたい。古い金庫だったけど、製造メーカーとか製造型番から調べられて」
そうすると、縁のない番号に語呂合わせをあてがったりしたわけではなく、自分で覚えやすい番号を設定できたわけだ。
金庫に貼り付けられた紙は間違いなく暗証番号を意味するだろう。ただ、そのまま番号を張り付けたのでは鍵をしていないのと変わらない。
自分しか知りえない番号を守り続けるためには、歳を取っても思い出し続けられる〈自分なりのルール〉を持っていたはずだ。
「おじいさんって、囲碁とか将棋とかやってた?」
突然投げられた直球の質問に琴羽野さんはかわいそうなくらい狼狽する。
「えっ? えーと……。確か……将棋はやってた気がする。というか、和室の押し入れに盤と駒と『なかとびぐるまをさしこなす本』っていう本も何冊かあった気がする」
(それは、佐波九段の『中飛車(なかびしゃ)を差しこなす本』のことだな。……僕も持ってる)
「ありがとう」
そうすると、想定した番号の裏付けがかなり高まった。
将棋でいう天王山とは盤面の中央部分、俗に5五の位と呼ばれる枡目のことを意味している。
歩数はおそらく、歩いた数のホスウではなく、歩の数――歩兵の駒の数のことだろう。すると、敵味方の双方9枚ずつで合計18枚となる。
ここまでで、55、18という数が一旦浮かび上がってくる。そして、『戦場の下』。
将棋で戦場と言えば、将棋盤のことだろう。その下には盤の脚がある。その脚は〈クチナシ〉が象られている。
昨日、リビングにあるPCで色々と調べてみたところ、クチナシ(サンシシ)は黄疸の症状に効能があるという記述が見つかった。
琴羽野さんのおじいさんの症状は黄疸のそれとよく似ていた。死因も肝不全だったことを考えると、生前に日常的にサンシシを飲んでいて、暗号に使うことを思いついたという可能性はそれなりに高いように考えたのだ。
55、18、そしてサンシシ(344)。
「5518344、もしかしたら、最後の344はクチナシがひっくり返っているから5518443かもしれないけど」
少なくとも、失敗しても時限爆弾のように爆発することは無いはずだ。
「早速、試してもらうね」と自宅にいる母親へ通話している様子をドキドキとしながら見守る。高校受験の合格発表が再来したかのように鼓動が高鳴り続けている。
しばらく、静かな時間が流れる……、そして。
「――っ! 開いたって!」
「おぉっ!」
二人して思わず歓声を上げる。
速報によると金庫の中には、土地の権利書や株券と一緒に、似顔絵や小物をはじめ、家族がこれまでにおじいさんにプレゼントしたものがぎっしりと大切にしまわれていたようだ。
家族が大好きだったのだろう、自分の最期を何となく感じて、大切な一日一日を宝物と一緒に宝物の近くで過ごしたかったのだろう。
「おじいちゃん……」
琴羽野さんの眼の端に、光るものが見えた。しかし、それは悲しさからは格別した、別の感情から生まれているもののような気がした。
「瀬田くん、本当にありがとう。今度、きっとお礼するから……」
純粋にパズルが解けた喜びもうれしかったし、家族のありがたみを再確認させてくれたのもうれしかったけど。
人からありがとうって言われるのもやっぱり、嬉しいなと思った。
*****
3時間目の英語の授業が終わった。
高校の授業は、教室移動が面倒だ。中学のときは、これほど頻繁に移動した記憶はない。
(次は……、また1階に戻るのか)
午前中からこんなに移動をしていると、弁当の質量に不安を感じる。果たして、十分なエネルギーを補えるだろうか。頼れる炭水化物の塊――コロッケパン――を補充する計画など立てておいたほうがいいかもしれない。
(うん? なんだこれ?)
席を立つ前に、机の下を確認すると、見慣れないノートが置いてあるのに気付いた。
(僕のはここにあるしな……)
おもて表紙を見ると、〈4組 蒼井妃冨〉とあった。下の名前は難読だけど、苗字はアオイさん、で当確だろう。
4組なら、1組に戻るルートの途中で寄るとしてもそれほど徒労ではない。ここはひとつ、届けてあげるのが紳士と言うものだろう。
階段を降り切った後、右手側に4組はある。
「ちょっと、すみません、蒼井さんって今いますか?」
教室の入口で、立ち話をしていた女子3人組に話しかける。昨日までに、美月とそれなりに会話を重ねたせいか、思ったよりも自然に会話ができたことに自分自身驚いた。
「あ、いるよー。呼んでこようか?」
「いや、そこまでの用事じゃないからいいです。これ、ノートの忘れ物っぽいので。渡してもらえますか?」
「そういうことね。OK」
英語ノートを手渡すと、僕は4組を後にした。
今日は、朝から着実に善行を積んでいる気がする。これは、きっとよいことが起こる予兆なのではあるまいか。
(なんてこった。まさか、ど真ん中に埋め込んでくるとは……)
よいことどころか、楽しいはずの昼食の時間は、突然襲ってきた厄災により崩壊した。きっと、かつて大繁栄し、突如理不尽な隕石によって絶滅した恐竜達も似たような感情を抱いたことだろう。
そう。好物の鶏の唐揚げの中心部に、僕の不倶戴天の敵――ピーマン――が何故か入っていたのだ。
思い切ってほお張った僕も完全に油断していた。三国志で言えば、勢い良く追撃をかけたものの、銅鑼の音と共に待ち伏せを喰らった負け軍師のようだ。
咀嚼したものを出すのはさすがに憚られた。思い切って、ペットボトルの緑茶で流し込む。
(はぁ……。ヒドいめに合った……)
敵ながら天晴れだったのが、市販の唐揚げそっくりだった点だ。僕がピーマンを拒絶するのに比例して、母の加工技術が飛躍的進歩を遂げているのを感じる。ノーベル食品工学賞がもしあったなら、一躍時の人になれそうだ。
とはいえ、喉もと過ぎればなんとやら。せめて、胃酸にもまれてもがき苦しんでいる(?)宿敵――ピーマンの悲鳴を夢想しながらうたたねでもしてるか。
そう思い、机に伏せようとしたが……。
「瀬田くん、4組の福路くんが呼んでたよ」
(袋? 復路?)
うたたねのチャンスはあっさりと失われた。昨日の女子が僕のところにそう告げに来たのだ。このパターンはまさか……。
廊下に出ると、銀縁メガネをした男子生徒がおずおずとしながら廊下に立っていた。
「えーっと、君がフクロくん?」
「ということは、君が噂のセタくんなんだねっ」
フクロくんはそういう性格なのか、「こういう者です」と言うと、生徒手帳に書かれている名前を名刺のように差し出して自己紹介をしてきた。
(福路、浩二……ね)
名前を確認してから見上げると福路くんの表情に、昨日の琴羽野さんと同じものを感じたので、念のため確認してみる。
「もしかすると、何か相談事だったり……」
「うおっ。さすが、名探偵だ!」
これは、うかつだった。自らハードルを高くしてしまう結果となってしまった。
福路くんは目を輝かせたかと思うと、次の瞬間には神妙な顔つきとなり顎に手をあてながら話し始めた。
「実は、数日前から彼女の態度が急に冷たくなった気がしてて……。思い当たるふしが全然無くて、八方塞がりなんだ」
「へ、へぇ……」
これまで奇跡的に相談事を解決へと導けていた僕だったけれど、恋愛沙汰の問題となると、これは全く力が及ぶ気がしなかった。
女の子の気持ちなんて、山の天気のようなものだろう。きっと些細なことなんだろうけど、本人にはとても重要で、そんなこと第三者の僕が予想できそうな気がしない。
さりげなく、当人に聞き込みをするにしても、見ず知らずの女子に近づくのは非常に難易度が高いように思われる。奇跡的に、美月が知り合いで、仲介をしてくれるとかがあれば話は別だけど。
「ちなみに、その彼女っていうのは、4組のアオイヒトミっていうんだけど。知らないよね……」
「えっ?」
「えっ!?」
僕の反応に、福路くんも驚く不思議な状況になってしまった。
アオイ、ヒトミ? もしかして。
「知ってるかも! えーと、ヒトミのヒが女偏に己のヒだったりする?」
「そうそう! えっ、なんで知ってるの?」
僕は、さっきの英語ノートの忘れ物の件を簡潔に話した。「納得納得。小中の頃から忘れ物おおい子だったんですよね……」としきりに頷いている。どうやら、人物像は一致したようだ。
入学式を終えてまだ数日しか経っていない段階で、「彼女の態度が冷たくなった」という関係とのことだから、ある程度予想はできていたが、そういうことだったか。
(それなら、もしかしたら少し取っ掛かりがある……かな)
依然として不安感は拭いきれないが、ここで無下に相談を拒否するのも憚られた。高校生活は始まったばかりなのだ。仮に解決できなくても僕に損はないし、もし解決できたらできたできっとプラス評価となるだろう。
「うーん、じゃあちょっと調べてみるから」
「本当かい!? それはとても助かるよ」
「まあ、でも。あんまり、期待しすぎないでね」
保険をかけておこうと思って被せようとしたセリフをを聞き終わるよりも早く、福路くんは足取り軽く立ち去ってしまった。
どうやら彼氏の方もけっこう早とちりしそうなタイプみたいだなぁ。
高校生としての任務から解放され、放課後になった。
慣れた足取りで将棋部の部室に向かい、手際よく、盤と駒を準備する。
春のうららかな日差しを浴びながら、美月はまだだろうか、と思いを馳せる。
って。
良く考えたら、仮入部期間は既に三日目に突入してしまっている。美月へのレクチャーはそれなりに充実した時間であることは否定しないが、それは平日の放課後である必要は無い。今日こそ、なんとか別のつながりを作って軽音楽部で音楽活動をスタートせねば。
僕は、駒を並べ始める。美月が来たら、いきなりレクチャーに入ってしまう作戦だ。余計な時間は極力カットだ。
ところが、駒自体は初形に並べられたものの、妙にしっくりこない。
もしやと思い、8つある駒箱とその中に入っている駒を改めると、どうやら何種類かの駒がごちゃまぜになっているようだ。
将棋の駒にも、材質や書体など様々ある。単純に使うだけならば役目として問題はないけれど、なんだかこうすっきりとしない感じだ。
あれこれ見比べながら、盤に広げた1組とその他7組を照合していく。
(あぁ、何やってんだろう。こんな状態で美月が来てしまったら、作戦台無しじゃないか……!)
噂をすればなんとやら、幸いにもちょうどすべてが終えたくらいに美月は部室に現れた。
「あ、今日はもう並んでる」
「ん、ああ。ちょっと時間があったから」
(はー、作戦無事成功……。ってもう疲れてどうするんだよ)
そう思ったのもつかの間。
椅子に座って盤面を見回した美月はぽつりと一言「あれ? いつもと違う」などと不思議なことを言う。
「え? 違くないよ。いつもどおりだよ」
人生でこれまで、何度、この初形を並べてきただろうか。間違えるなどと言うことは断じてありえない。それだけに、僕も少しムキになって反論した。しかし美月も譲らない。
「ねえ、大丈夫? 駒だよ駒。〈王将〉じゃなくて、〈玉将〉になってる。」
「はい?」
そう言われて、やっと僕も気づいた。確かに、美月の方だけ〈玉将〉と書かれた駒が並んでいたのだ。
しかし、それは。
「ああ、それはそれでいいんだ。欠陥じゃないよ」
「……?」
美月は、眉根を寄せて「訳が分からない」といった表情を浮かべている。
美月のように、知らない人は知らないし、僕のように、知っている人は当然知っている事実。
将棋の駒には、〈王将〉と〈玉将〉の二種類が存在する。通常の駒のセットならば、一つずつ入っている。
〈王将〉という言葉の方が圧倒的に耳馴染みがあるだけに、玉将という言葉自体「王将の間違いでは?」という考え方は確かに自然かもしれない。
しかし歴史的にみると、むしろ初期の将棋では〈玉将〉しかなかったとさえ言われている。現存する最古の駒には玉将は3枚含まれていたが、〈王将〉は一切含まれていなかったという事実もある。
元々、将棋の駒は『お宝』を現していたようだ。〈金将〉〈銀将〉は言わずもがなゴールドとシルバー、桂馬は肉桂(シナモン)、香車は香木といった具合だ。
この流れでいえば、〈玉将〉の玉は宝玉のことだ、と言う説を聞いてしまうと〈王将〉より〈玉将〉のほうがしっくりする気さえする。
その後、時代が進むにつれて、王と玉の字が似ていること、三国志にも登場する『天に二日なく、地に二王なし』――王は二人もいらない――、といった趣向と交じり合い、いつの間にか〈玉将〉と〈王将〉を1枚ずつ使うようになったと言われている。
さっき、8組の駒箱を再整理し終えたけど、昨日までは〈王将〉と〈玉将〉の組合せがごちゃ混ぜで使っていたのだろう。
といった内容を僕は淀みなく話す。
が。
……美月さん、目付きが鋭いままなんですけど。
「そんな説明、今まではなかったよね?」
将棋を指している人間にとっては、『どっちでもいい』ことだ。
しかし、この将棋初心者にはそれは通じなかった。元々、猛禽類のように鋭い美月の目線は今にも襲い掛かってきそうに見え、僕は思わず視線をそらす。
ここは一つ、怒りの矛先をそらすために、架空の叔父さんに登場いただくことにした。
「まあまあ、落ち着いて。親戚に『大』きいに『志』でタイシっていう名前の叔父さんがいて、しょっちゅう漢字を『太』いに『志』ってに間違えられたり、ヒロシって呼ばれたりしてるんだけど、『どっちもそんなに変わらんしな』ってぜんぜん気にしていないんだ。確かに、」
「……」
が。
……美月さん、目付きがもっと鋭くなってるんですけど。
「……デコピン」
「はい?」
「デコピン1発で勘弁したげる」
……どうやら、判決が下されたようだ。まあでも僥倖だろう。デコピン一つでこの局面が打開できるならありがたい。表面上は「しょうがないな」という表情を作っている僕の顔に、美月の指が伸びてきて――。
ビシィッッッッ……!!
「っ痛あっ!!」
額に、衝撃が走る。なんてパワーだ。とても年頃の女子のものとは思えない。骨伝導のせいなのか、凄い音がした気がする。脳に悪影響が出なかっただろうかと不安になる。
昔から、将棋盤に遠慮なくビシバシ駒を叩きつけていたが、その報いが今まさにまとめてやってたとでもいうのか……。
その衝撃を受けて、身体のバランスを崩し、椅子ごと後ろに倒れこんだ。そして、黒板の下の壁に身体がぶつかり、その衝撃でちょうど上にあった黒板消しが頭の上に落下してくる。
僕は額の苦悶、チョークの粉でむせてしまう。なんとも情けない姿だ。しかし、悲劇はそれで終わらなかった。
鼻がむずむずする。
(やばっ、よりによってこんなときに……!)
僕の願いも空しく、それは起こる。
「――っぐわあっくしょおおおぉい!!!!」
豪傑の咆哮のような爆音と、対比的に訪れる静寂。
人に言えない恥ずかしい秘密の上位に位置する”見かけによらず、くしゃみが派手”が、知られたくな人物に知られてしまったのであった。
「……っ。ははっ」
見上げた美月の顔は、年相応の女子の顔で笑っていた……。左頬には笑窪も見える。
(……なんだよ、フツーに笑えるんじゃん)
そして、その笑顔を見て反則的に可愛いと感じる。瀬田桂夜は織賀美月に惚れているのだ、と何故か冷静に感じてしまった。思わず、額の痛みや恥ずかしさも忘れてその笑顔をまじまじと見つめてしまった。
しかし、それは刹那の出来事だった。
苦しんでいるはずの僕が急におとなしくなり、美月も、自分が無意識のうちに笑顔になっていたことに気づいたようだ。顔はいつもの無表情なものに戻っていた。
「……見た?」
「えっ?」
「笑ってるとこ、見たでしょ」
「え、あ、まあ……見たといえば見た……けど」
すると、美月はカバンを手にして、すっと立ち上がる。
「あたし、笑窪って嫌いなの。人に見られるのがヤなの」
(もしかして、いつも無表情なのって……)
そういう理由なのか? だとすれば、それはどれだけもったいないことか。
しかし、笑窪のできる人には、できる人なりの悩みがあるのかもしれない。笑窪のできない僕に、そういう人達に向かって単純に「笑窪万歳」と礼賛する権利はないのだろう。
表情こそ変わらないが、美月の眼と声には普段以上の力強さがあった。つまり、美月にとってそれは重要な事柄だというなによりの証拠だ。僕は圧倒されて、沈黙してしまう。
そもそも、僕だってさっきのくしゃみだけでなく、高校の同級生には大っぴらにしたくないことがいくつかあるのだ。
僅かな沈黙の時間のあと、「今日はもう帰る」そう言って、美月はすたすたと教室を出て行ってしまった。
引き止めるのは無理だったにしても、せめて「そんなことないよ」という気落ちだけでもなんとか伝えておけなかったものだろうか。それだけが悔やまれた。
しかし、一つ救いがあるとするならば。
美月は「今日『は』帰る」と言っていた。それは、明日も来る、ということの裏返しではないだろうか。それは、都合のよい考えだろうか。
結局、今日の二つの計画はあえなく両方とも完遂することができなかった。せめて、首の皮一枚繋がっていればと願うばかりだ。
さて、美月が去ってしまった今、この部屋にいる理由は全く無い。手早く撤収しないと、ヤツが姿を現すおそれがある。
「ハロー!!」
(間に合わなかったか!)
こういう時ばかり直感が優れているのも空しいものだ。現れた泉西先生を見て、僕は小さくため息をつく。
「少ね……いや、瀬田よ。今、例の可愛い女子生徒がスカートを翻して走り去っていったが、痴情のもつれか? ……痴情? お前、ここは学校だぞ! 聖職者として断固許さん! お前の通知表の現国を史上初のマイナス値にしてやろうか?」
「はいはい……、聖職者の泉西先生は、常にまず落ち着いてください……」
「ふー……、ふー……」
僕は、興奮した泉西先生にでもわかりやすいように、噛み砕いて先程の出来事を話してみた。
「なるほどな。国語教師の立場からすると、テストだったらペケだな。」
「ペケ、ですか」
「まあ、男としての立場なら『どーでもいい』だがな。相手は女子だぞ。別種族だぞ。点があるとかないとか、そういう細かいの気にするんじゃね?」
泉西先生はどうやらナイスアドバイスができたと満足したのか、美月が不在となったからか、それだけ言うと大人しく教室を出て行ってしまった。
(僕に絡んでくるやつは、どうしてこんなにマイペースなのばっかりなんだろう……)
なんだか、高校生のうちにストレスで毛が抜け始めるんじゃないかと不安がこみ上げてきた。ただでさえ、父の頭頂部が最近危なくなってきている今日この頃だというのに。
誰もいなくなり、すっかり静かになった教室の中で僕は一人片づけを始めた。駒と盤をしまい、ドアの施錠をする。カチリという金属音がした時、不意にさっきの泉西先生の言葉が浮かび上がってきた。
――点があるとかないとか――
――細かいの気にする――
そして。
今度は、自分の頭の中にもでカチリという音が聞こえた気がした。
僕は科学部の部室を尋ねていた。入口から福路くんの姿を伺っていると、白衣を着た福路くんはこちらに気づいたようで、先輩に一言二言断ってからこちらにやってきた。
「瀬田くん、もしかして?」
「うん、なんとなく分かった気がする」
「えっ、本当に!?」
福路くんは実のところ、それほど期待はしていなかったのかもしれない。驚き具合からそう思えてしまうが、それは些事だ。まあ気にしないこととする。
僕は、鞄からルーズリーフを一枚取り出して、「ここにさ、蒼井さんの名前、フルネームで書いてもらえる?」とペンを渡して促した。
「? そのくらい、なんてことはないけど……」
福路くんは不思議そうにしながらも、一文字ずつ字を書いていく。
蒼 井 妃 富
「音は簡単なんだけど、字が結構難しいんですよね……。さすがにもう書けるようになりましたが」
福路くんはペンとルーズリーフをこちらに返しながらそう言う。
ルーズリーフを受け取った僕は確信する。やはり、これが原因な気がする、と。
「ありがとう。でね、言いづらいんだけど……」
「?」
僕は、福路くんの文字の隣に一つ字を書いて、続けた。
「名前の漢字、間違ってると思うんだ……」
「えぇ!?」
福路くんは本気で驚いたようで、ルーズリーフをひったくると自分の文字と僕の文字をまじまじと見比べる。
「点が……、無いっ!?」
「実は先日、蒼井さんの名前を見る機会があったんだけど、トミは上の点が漢字の方だったんだ」
『富』と『冨』、どちらも『トミ』と読み、形もほとんど同じで非常に紛らわしい。
福路くんは「まさか、こんなワナが仕掛けられていたとは……。ということは、中学のときから間違えていたのか……」と呟き、わなないている。
彼自身が言ったように、蒼井さんの名前は音の方は非常にシンプルで間違えようが無い。しかし、文字の方はなかなか手強かったのだ。
『蒼』や『妃』という文字は日常生活ではなかなか目にする機会がない文字で少し珍しい。さらに、これを「間違えないように……」と強く意識すると、相対的に『冨』の方が疎かになってしまったのだろう。
これが、王と玉のようにせめて読み方も異なっていれば、今回の悲劇は生まれなかったのだろうけど。
「なんとか、仲直りする方法も考えないとだなぁ。……そうだ! 親戚で『富』の字が入る叔父さんがいて、間違えてしまったんだ……、とかどうでしょう」
「うん。経験者の意見を述べさせてもらうなら、素直に謝った方がベストかな」
僕は、額の赤くなったデコピン跡地を指差してアドバイスした。
振り返ってみると、今日も色々と山あり谷ありな一日だった。
琴羽野さんの依頼解決から始まり、ピーマン事変、美月のデコピンおよび笑顔、そして福路くんの依頼解決、と。
家に帰り、ドアを開けると、玄関にまで美味しそうなあの匂いが充満していた。
(カレーか!)
カレーは僕の大好物である。365日カレーでも構わない。来世はインド人になるつもりでいるから、地理の授業中の度に、地図帳でインドの都市名をインプットことにしている。
台所に入ると、匂いはますます強くなる。僕レベルになると、この段階で今日はチキンカレーで具にジャガイモと玉ネギとほうれん草が入っていることまでお見通しだ。
僕は弁当箱を夕飯の支度に勤しんでいる母に手渡した。母は僕の弁当箱が空になっているのを確認すると、小さくガッツポーズを取っていた。
(くっ……。明日は勝つ!)
妙に挑戦心を煽られてしまう。母も、なんだか当初の目的を忘れて、純粋にバトルを楽しんでいるように思えてきた。
小説『Spring in the Spring =跳躍の春=』(4/5)に続く
小説『Spring in the Spring =跳躍の春=』(2/5)
*****
白髪混じりの頭に汗を浮かべ、後退した額には深いシワ、苦しそうな表情を浮かべる初老のおじさん。
その人が、僕のヒーローだった。
*****
第二章 『火曜日』
「瀬田! 昨日はありがとな」
翌日、登校してきた勝田くんの笑顔を見て僕は肩の荷がすっとおりた心地がした。
初っ端の笑顔がそのまま答えだったようで、新規開拓はの案はゴーサインが出たとのこと。親父さんを含めて急いで準備を進めているのだという。
「ちなみに、ここだけの話なんだが、誰もが知っているあの野菜が真っ白になった新種を国内初で取り扱うってことらしいぜ」
「そ、そうなんだ」
緑色のアスパラガスと白いアスパラガスを頭に思い浮かべ、なんとなくトマトやらホウレンソウやらを白く変色させてみたがあまりいいイメージにはならなかった。
見慣れて、それが日常になれば当たり前になるんだろうけど。
白い何かの野菜がブレイクするか否かは一旦おいておき、勝田くん的には父親から小遣い増額の交渉材料ができたと喜んでいる状況で、何よりだ。
「何か輸入したいものがあったら遠慮なく言ってくれよな! うちは法に触れるもの以外は何でも取り扱ってるからさ」
と白い歯を見せながらニッと笑う。
「ははは、ありがとう」
気持ちはうれしいけど、今のところは石油とか南京豆とかイージス艦とか、僕は特に興味はないんで遠慮しておくことにする。
*****
授業も3時間目に入り、少々集中力が途切れてきた。しかも科目は英語ときたもんだ。英語なんて、将来は万能翻訳端末が流行して勉強の必要なんてなくなる、というのが僕の予測だ。優秀な人間は、優秀な道具や人材が使えれば良いだけだ。本人がスーパーマンになる必要はない。ほぼ父の受け売りだけど。
窓の外のグラウンドを何気なく見下ろすと、体育の授業をやっているのが見えた。ジャージの色からすると、同じ一年生のようだ。
(ん? あれは?)
屈伸をしている一人の女子に目が留まる。あのポニーテール、どこかで見覚えが……。
(あ、美月!?)
「おいおい、速すぎだろっ!」
美月は脚が恐ろしく速かった。陸上部の男子と同じくらいのレベルといっても過言ではないかもしれない。
昨日、間近で所作を眺めたりしていたが、運動の類が特段優れているような雰囲気は無かった。小柄で、むしろ苦手な方かと思っていたので、そのギャップに驚嘆だ。
(……おや?)
教室の様子がおかしい。少しざわついて、皆、僕の方を見ているようだが……。まさか……。
そのまさかだった。どうやら、思っていたことが口に出てしまっていたようだ。高校入学早々、なんという失態だろうか。しかし。
「オゥ……。私は、もう一度読みます、ゆっくりと。なぜなら、生徒の中の一人から、要求を受けたためです。When I was young, I'd listen to the radio……」
(危なかった……!)
幸い、英語の石井英美先生は僕が『教科書を読むのが速かった』と勘違いしてくれたようだ。
それにしても、美月の謎が深まる。あれだけの運動神経なら、運動部からは引く手数多だろう。それなのに、貴重な仮入部期間を将棋部などで消費している。
今日、思い切って聞いてみようか。いや、それともそれこそやぶ蛇だろうか。
*****
昼休み。弁当の時間だ。
(母め。甘い、甘すぎる!)
玉子焼きの味付けが塩か砂糖かといった低レベルな話ではない。甘いおかずはおかずに非ず、という点は母と僕の数少ない思考の共有事項なので問題ない。
僕は、巧みな箸さばきで弁当箱の中の焼きそばから細長いピーマンをススス……と抜き出していく。我ながら至芸の技だ。この域まで達すると、母が後天的に授けてくれた才能であると言ってもいいだろう。
僕はピーマンが大嫌いだ。不倶戴天の敵だと認識している。人類は豊かになり、美味しい食材も多々あるのに、何故あんな青臭くて苦いものを食わなければならないのだ。全くもって理解に苦しむ。
小学生時代や中学生時代は給食制だったので、毎日ピーマンが出てくるような悲劇は起きなかった。(そんな悪逆を考える栄養士がいたなら、民事訴訟を起こすつもりだったが。)
しかし、大矢高校は給食制ではない。弁当を持参するか、買い食いをするしかない。
非情にも先例(会社勤めの父のことだ)に倣い「買い食いしたければ小遣いから出すこと。※木曜日は除く」というルールが一方的に発布されたため、毎日の昼食は弁当を作ってもらう、ということにはなったのだが。
ここに、ピーマンを食べさせようとする母と、それを拒む僕のランチバトルが勃発したのだ。
最初のころは、堂々とピーマンの肉詰めやチンジャオロースーといったあからさまなメニューを展開してきた。しかし、僕がきっちりと残し続けるものだから、徐々にカムフラージュは巧妙になっていった。
ピーマンを麺と同じレベルまで細切りにし、麺と絡めてきたが視認できる以上、僕の眼はごまかせない。
さて。腹も満たされたことだし、勝利の余韻に浸りつつ、午後の授業まで昼寝でもするか。
そう思い、机に伏せようとしたが……。
「瀬田くん、2組の琴羽野さんが呼んでるよ」
まだ名前を完全に覚えていないクラスの女子が僕のところにそう告げに来た。
(はて、コトバノ?)
聞き覚えがない名前だから、別の中学出身の子だろう。
廊下に出ると、小柄な女の子がおずおずとしながら廊下に立っていた。体型は美月と同じくらいだが、やや丸顔をしたおとなしそうな子だった。
「あの……。あなたが、瀬田くん?」
「あ、えーと。そうだけど?」
「ちょっと……ここじゃ話しづらいから……」
そういって、自己紹介もせぬまま廊下をすたすたと歩き始めてしまった。方向は別館の方だ。確かに人は少なそうではあるが。
思わぬ急展開に僕は思考をめぐらすが、彼女の目的が今ひとつ分からない。まさか、初対面で『告白』ってことは無いとは思うけれど。
それはまあ、一目惚れという可能性だってゼロではないだろうが……。
昨日の自分のことを思い出すと、説得力が急速になくなってきた。
「はじめまして、1年2組の琴羽野彩です。実は相談したいことがありまして……」
「相談?」
「あ、はい。私が困っているのを、勝田くんが『すごい頭が切れる奴がいるんだ』って紹介してくれたので」
あぁ、なるほど、一応腑には落ちた。けれど、勝田くんもなかなかプレッシャーのかかる紹介をしてくれるじゃないか……。
琴羽野さんは、制服の胸ポケットから四つ折の紙を取り出して、それを広げて見せてくれた。
(なになに……?)
――天王山、歩数、戦場の下――
「数字はたぶん7桁だと思うんです。シリンダーが7つだから……」
シリンダー? 一種の暗号だろうか。
琴羽野さんが順を追って説明してくれた。
先日、おじいさんが肝不全で亡くなり、遺品に金庫が見つかったこと。
金庫は施錠された状態だったが、おじいさん個人のものであり、家族の誰もその暗証番号を知らなかったこと。
金庫の脇にこの四つ折の紙が貼り付けられていたこと。
物理的にバーナーなどで金庫を壊すこともできるそうだが、おばあさんとしては『金庫もおじいさんの大事な遺品の一つだ』と主張して物理破壊に難色を示していること。
「おじいちゃん、入院は絶対しない、乾布摩擦と漢方で治すんだって言って聞かなくて……。でも、大好きなお酒もやめられなくて、だんだん目とか皮膚も黄色くなっていっちゃって、最後は……ぅぐっ、うっ」。
最期を思い出してしまったのか、突然泣き出しそうになる琴羽野さん。
って、こんなところを誰かに見られたら、絶対にものすごい尾鰭のついた噂話を作られてしまう!
僕は慌てて、話を元に戻そうとした。
「あ、えーと。で、何か番号を試してみたりはしたの?」
「ご、ごめんね。お父さんは、明智光秀と羽柴秀吉が戦った山崎の戦いのことだろうっていうんだけど。
1582年6月13日で1582613では開かなかったんです。
旧暦じゃないのかもと思って、7月2日にした1582072とか1582702もだめで……」
「うーん……」
僕は腕組みをして廊下の天井をぼんやりと見つめながら考えてみる。いきなり、他人の家の7桁の数字と言われても、難易度が高すぎだ。
「難しいですよね……? あの、無理ならいいんです」
「いやっ、もう少し時間が欲しいかなって」
「あっ。そ、そうですよね……。」
正直なところ、まったく勝算はなかった。けれど、見たところ積極的なタイプでなさそうな琴羽野が、さっきまで見ず知らずだった僕に相談をするくらいには大事なことなのだ。
すぐに白旗を揚げるのは失礼だと思ったのだ。
さて、5時間目とホームルームも終え、放課後。部活の時間に突入である。
僕は、盤と駒を教室に運び込み、待った。が、なかなか来ない。
(昨日の、口から出まかせってことはないよな。こっちは、仮入部までしたんだけど)
なんだか落ち着かない。あれ、デートの待ち合わせってこんな気持ちなんだろうか。世の中の男女はこんな苦しさをしながら、恋愛しているものなのか……?
僕の心が微振動していると、
「あ、ちゃんと来てる」
相変わらず無愛想な表情だったが、約束どおり美月は今日も現れた。しかし、昨日コミュニケーションの機会があったせいか、声や態度が微妙に親近感を含んでいるような気がした。あくまで僕目線でですけど。
「約束だったからね」
あくまで、表情は「しょうがないから来たよ、本当はすぐにでも軽音楽部へ行きたいんだ」という演出をしてみるが、内心は勿論まんざらでもない。
美月は「じゃ、よろしく」と目の前の椅子に腰を落とした。
「じゃあ、今日はルールを説明するよ」
今日はテンポ良く行きたいところだ。あの面倒な顧問がやってくるまでに、ルール説明を済ませ、さらにはうまいこと美月の携帯端末の番号など、何らかのコネクションキープ確立まで持ち込む。
僕の脳は本日、フル回転で頑張らなくてはならない。
ルール
A:交互に指す。パスは無し。二連続で指すのはダメ(反則)
B:自分から王手にかかりにいっちゃダメ(反則)
C:相手の陣地(歩のライン)まで進んだら『成り駒』になることもできる。
ただし、持ち駒の場合は打った瞬間には『成り駒』にはなれない。
D:動ける場所のない駒を作っちゃダメ(反則)
E:二歩…縦のラインに自分の歩が二つ存在してはダメ(反則)
F:打ち歩詰め…持ち駒の歩を打ってトドメをさすのはダメ(反則)
G:千日手…同じ局面が4回現れたら(引き分け、指し直しの場合は先手後手入れ替え)
H:王手がかかってる状況での千日手は、王手を掛けている側が負け。
I:持将棋…相入玉などで王を詰めることで勝負を決められそうにない場合、点数計算で勝敗決める
→飛車・角は5点、王以外の駒は1点として、24点未満の方は負け。両者24点以上なら引き分け。
黒板にざっとルールを書き連ねていった。昨日の夜、少し予習をしておいたので、かなり簡潔に書けたと思うが。
「AとBはなんとなく分かるからいいよね。CとDは昨日、駒の種類と動かし方やったときに少し触れたと思う」
「うん」
「EとFは、実際に場面を見れば一瞬で理解できると思う。」
「うん」
「GとHはちょっと珍しいケースなんだけど、たとえばこんな風に、自分のほうは絶体絶命で、相手を詰めないと負けになってしまうケースがあったとする」
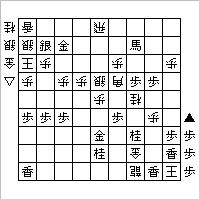
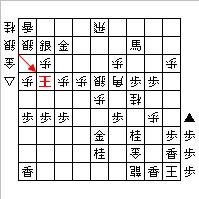
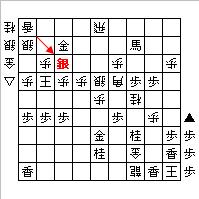
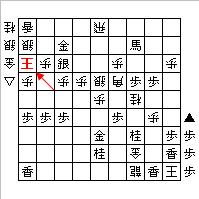

「お互いに、ベストな手を指そうとして結果として同じ局面が繰り返されるケースがあって。こういうのが千日手っていうんだ。特に、この場合は王手をかけちゃってるからHのケースで先手の負けになる」
「攻めてるのに負け扱いになるわけ?」
(言われてみれば、攻めているのに負けになるなんて結構不思議なルールだよな)
昨日の初手9七角や桂馬の動きのくだりも思い出し、「そういうものだ」と覚えてしまうとなかなか疑問を持つ機会がなくなってしまう一例だなと改めて感じる。
「Iのルールは変わってるね。急に数値が出てくる」
「数値?」
「要するに、駒がお金みたいになってるわけでしょ?」
「そうだね」
お金、か。
将棋をはじめた頃は、駒の価値をイメージするために、歩は1円、香は5円、桂は10円……と父から教わったものだ。不意にそれを思い出した。
「なんかさ、この板って味気ないよね。少しガタガタするし」
黒板の撮影を終えた美月は手元にあった将棋盤を指先でぐいぐい押してそんなことをいう。
「それは下の机がガタガタしてるからだよ。和室と脚付き盤があればね……」
和室はおそらく、泉西先生の言うように茶道部か華道部あたりが優先的に使っているだろうし、学校の備品で脚付き盤があるとは思えない。
「ケーヤの家には脚付いてるのあるの?」
「そりゃもう」
先祖代々、男系はみな将棋が好きだったが、僕はとりわけ棋力が高かったようだ。僕が初段をとった祝いに奮発して両親が買ってくれた脚付き盤がある。ただ、今は諸事情によりウォーキングクローゼの片隅に蹲っている状態だ。
「へぇ。携帯カメラで撮ってきてよ」
何がそんなに気になったのか、美月はそんなお願いをしてきた。取り出すのが少し大変だろうなとは思ったが、そのくらいであれば容易い。二つ返事で引き受ける。
「さて、そろそろ帰るかな。また明日ね」
「……あ、あぁ」
美月はカバンを手にして、立ち上がる。その全身を改めて見ると、華奢ではあるものの肢体も整っていた。体育の授業で見せた動きは見間違いではなかったか。
一瞬、変な目で見ていると思われなかったかと気にするが、特に気づかなかったようで「じゃあね」と、何事もなかったように教室を出て行った。よかったよかった。
「……いや、よくない!」
今日こそはと思っていたのに、またしても連絡手段が確立できていないじゃないか。
まあ、まだ火曜日。明日もここに来たとしてもまだ2日間残っているからまだセーフといえばセーフだ。
一人きりになると、この部屋は急に静かになる。壁掛け時計を見ると、非常に中途半端な時間だ。今からじゃ、きっと軽音楽部はもう無理だろう。
(今日は僕ももう帰るかな)
家に帰って、琴羽野さんのおじいさんの暗号のことでも考えてみるか。となれば、行動は素早く。厄介な顧問がやってくる前に。
僕は手早く盤と駒を片付けることにした。
*****
帰宅して、僕は弁当箱を夕飯の下ごしらえに勤しんでいる母に手渡した。母は僕の弁当箱の中に、麺のように細切りになったピーマンが残存しているのを確認すると、小さく舌打ちをしていた。
なんだか、母の闘志に火をつけてしまったような気がして身震いがする。
今日は随分しゃべったせいか、喉が渇く。冷蔵庫を開けると、クーラーポットが入っていたのでそれを取り出して茶色い液体をコップにカパカパあけた。
ふと、暗号のことを思い出していた。
――天王山、歩数、戦場の下――
ひらがなに変換したり、アルファベットに変換したりしてみるが、糸口になりそうなものではなかった。
(区切るところが違うのか? 天王山、歩数、戦場は全部感じで7つある、それらの下……っていう可能性も)
あ、そういえば、美月に脚付き盤をカメラで撮るって約束してたっけな。あれこれ考えながら、僕は茶色い液体を流し込む。と。
舌と喉に激しい違和感。
「げぇっ! なんだこの不味いの!」
おそろしく不味い液体だった。てっきり、麦茶か何かだと思っていただけに、完全にノーマークで余計に不味く感じた。
「あら。それ、昨日お父さんが自作した漢方ジュースよ。なんかセンブリとかサンシシとか入れてたみたいだけど」
センブリって、よくテレビの罰ゲームとかでやってる不味い奴じゃないか! しかし、サンシシとはなんだ?
「サンシシ?」
「クチナシの実のことみたいよ。漢方だとそう呼ぶんだって言ってたわ」
「サンシシねぇ」
脳内の要注意食品リストのセンブリ項の隣に記しておくこととしよう……。
自室に戻ると、ウォーキングクローゼットの中の隅にあった脚付き盤を引っ張り出そうとする。上に荷物を積み重ねていたせいで取り出すのに難儀した。
久々に白光のもとに晒した盤は、正直なところ、悲惨な状態に見えた。
所々に茶色いシミのような模様が浮かび、全体は飴色。黒色の升目も見えにくくなっていた。
(それでも、もう……決めたことなんだ)
うっすらと涙目になっていることに弁明するように、僕は写真を撮り始める。
(絵本だって、ぬいぐるみだって、新しいことに出会うたびに手放してきたじゃないか。それと変わらないじゃないか)
心の中の何かが決意の蓋を押し開けないよう、何度も自分に言い聞かせながら撮影を続ける。何度か試行錯誤するうち、一番まともに思える角度が見つかり無事撮影は完了した。
(あれ? 裏側は要るかな……)
脚付き盤の裏側も少し変わった趣向が凝らされている。明言はされていなかったが、結局欲しがられると、また後日この盤と向かい合わなければならないことが心配された。
(……念のため、撮っておくか)
フローリングを傷つけないよう、気を付けながら脚付き盤をひっくり返す。4つの脚が上を向き、〈血だまり〉が見えた。こうしてみると、生き物のようにも見える。
撮影を終えて、部屋の中を元通りに戻すと一息つく。写真も無事撮れたので、明日の準備は万全だ。
気持ちを切り替えていこう、と思った矢先。先ほどの裏返った脚付き盤がふいに思い出されて、同時に予期せぬ言葉たちが頭の中に〈跳躍(リープ)〉してきた。
(あ……、これってもしかして……)
小説『Spring in the Spring =跳躍の春=』(3/5)に続く
小説『Spring in the Spring =跳躍の春=』(1/5)
*****
風に 花の匂いが混じる頃 あなたとの物語ははじまった
*****
第一章 『月曜日』
寒い冬を越えてやっと咲いた桜が、早くも散り始める4月上旬。
季節は春、springである。springには〈跳躍〉といった意味もある。春は跳躍の季節。なるほど、なかなか的を射ている気もする。
まだ慣れない教室をぐるりと見渡せば、みな一様に機体とファン……じゃなくて、期待と不安をみなぎらせているように見える。
義務教育だった中学校から良くも悪くも開放されたのだ。誰でも大なり小なりの心境の変化は訪れていることだろう。
教室の教壇側の上部に据えつけられている壁掛け時計の針は、間もなく午後のホームルーム終了を示す時刻になろうかというところだ。
担任に急用ができたとかで、教壇の上では急きょ代理となった副担任が先日高校生活を始めたばかりの僕達に向けて、「き、君達の未来は、む、無限の可能性に溢れているっ……」などと成分の半分が無意味で構成された激励を発信していた。
(早く終わってくれ……)
それは、僕だけの感想ではない。周りを見渡してみると案の定、教室全体が『辟易した顔』のコピペを繰り返したような有様だった。
いや、仮にこの教師が前職コメディアンの経歴を持っており、卓越した話術をもっていたとしても変わりはなかっただろう。僕達は、面白い話や有益な話を期待しているのではない。ホームルームの即刻終了、ただその一点のみを期待しているのだから。
しきりに髪を撫でる者、脚を揺らす者、各々が『自身がストレスを感じた時にするしぐさを披露するタイム』を始めたようで教室の雰囲気も次第に重苦しさを増して行く。
奇声とともにこの教師に襲い掛かる者が現れやしないかと、何故か僕がそんな心配をしかけたとき、
「……それでは、あー、今日はこれでおしまいに、……とします。また、あした」
副担任の締めの挨拶とほぼ同時にキンコンカンコン、とチャイムが鳴りはじめ、安堵する。
いや、安堵している場合ではないんだ。
安堵さえもショートカットした鋭敏な生徒達は、予めまとめておいた荷物を手早く掴むと、蜘蛛の子を散らすように、勢い良く教室を飛び出していった。
僕も、流れに乗り遅れないよう、せわしなく教室を飛び出した。
廊下に出ると、早くも人の群れ。7つあるどこの一年生の教室も似たような状況だったようだ。
(しかしこれは、想像してたより、移動が難しそう……だ……)
第三者的に見れば、この高校にバイオハザードでも起きたのかと思われるほどの混乱であるが、ここ大矢高校においては毎年繰り返される当たり前の光景らしい。受験生のみならず、他校でさえ有名になっている現象のため、ここで戸惑っているような奴は『他国のスパイ』か『地球外生命体』として生徒会に尋問されるという噂もある。
と、多少大げさに言ってみたところで、その正体はなんと言うことはない。単に『部活動の仮入部期間スタート』なのである。それ以上でも以下でもない。普通は。
しかし、大矢高校での部活動というのはただのお遊びや時間つぶしではない。時として、高校生活だけでなく、後の人生にまで大きな影響を与えうる重要な位置づけと認識されている。その理由は大きく3つある。
1つめ。高校近辺にめぼしい娯楽施設や繁華街もないため、楽しみと言えば部活動に打ち込むくらいしかない。
2つめ。高校側も部活動に対して、比較的多額の予算を割り当てており、施設も備品もそこそこ充実している。そのためか、部活のレベルが全国的に高く、各分野での有名人をそこそこ輩出している。必然、各界からは常にウォッチされており、その道に将来進もうと野望を持つ高校生にとっては大きなキャリアとなる。
3つめ。部活を通じたカップル成立が非常に多い。多感な年頃の男女にとっては、これも重要だろう。場合によっては一番魅力的に映るかもしれない。
(しかし、網諾寺の初詣でもこんな混雑しないぞ……!)
まだ、校舎の構造を完全に把握していない新入生に加え、新入生の勧誘に必死になる上級生とが入り混じった結果、校舎内は複雑な攪拌運動の場と化している。なお、教師達はその光景を〈神の見えざる泡立て器〉と名付け、のんびりと教務室から茶をすすりながら観察しているらしい。なんとも他人事過ぎる話だが。
本来の部活動に支障がでないように、仮入部は人数制限を設けているところが多い。シビアな世界なのだ。
僕が狙っているのは〈軽音楽部〉。例年、人気ランキング5位には入る競争率の高い部である。部室は、別館最上階の一番端にある音楽室だ。僕の一組は一年の教室の中では一番音楽室から遠いロケーションにある。なんと、不遇で、長い道のりだろう。三蔵法師も真っ青だ。しかし、そんな荒行もバラ色の高校生活を思えばなんてことはない。非常に甘すぎる見通しかもしれないが、音楽をやる男はモテる!はずなんだ。
既に、春休みのうちに中古のエレキギターを購入して、練習も始めている。スタートダッシュに向けての視界は良好だ。「ああ、勉強もこのぐらい真面目に予習しておいてくれればよかったのに!」と成人した未来の自分からのメッセージがタイムリーぷして聞こえてきそうだが、今はサイレントモードまたは着信拒否だ。
明るい未来をモチベーションとして、僕は人ごみを掻き分けて進む。うん、段々慣れてきたようだ。別館への渡り廊下が間近に迫ってきた。とそのとき――、
「おーい! 瀬田っ!」
ざわめく廊下で、不意に名前を呼ばれて僕は思わず立ち止まる。人をかき分けかき分け、一際背の高い男が近づいてくるのが見えた。
あれは……。同じ美節中出身の勝田ダイ(かつただい)くんだ。勝田くんとは、確か中学3年の時に一緒のクラスだったが、それほど親密だったわけというほどでもない。
彼はいわゆるスポーツ好きなアウトドア派、インドア派の僕とは少し毛色が違うのだ。
そして、なぜ、よりによってこのタイミングで? 僕は訝りながらも、さすがに失礼になるので、表情にそれを浮かべないようにして彼を待つ。
「なんか、久し振り……だよな。ちょっと時間いいか?」
「え……。あ、あー、うん」
久し振り……だっただろうか。冷静に考えて、卒業式のあと春休みを挟んだだけだけど……。これが親父がよく口にしているシャコウジレイと言うヤツか? まあ、会話をしたかどうかで考えれば、確かに久し振りではあるなと僕は思うことにした。
「ちょっと、そこ入ろう」
とりあえず、この戦場のような廊下での立ち話は危険だということで、僕達は一旦近くの教室に入ることにした。
教室のドアを閉めると、外の喧騒は一段階小さくなった。あの狂騒の中に後でまた戻るのかと思うと、身が引き締まる想いだ。
「あれ? 随分と印象変わったなあ。まあ、今の方がカッコいいぜ」
「あ、ありがとう。ところで、何か用事が?」
「そうそう。悪いんだが、ちょっと協力してほしいことがあってさ……」
制服のポケットから携帯端末を取り出して、勝田くんはストレートにそう告げる。
せわしなく操作をし始めて、やがて「これなんだが」と携帯端末の画面をこちらに差し出してきた。
なんだろうと思い、覗き込んだ僕は、「……あっ!」思わず声をあげていた。
見間違いようもなく、それは将棋の初形――まだどちらも指していない初期状態だった。

それは、僕にとっては一番見たくない画像だった。それをきっかけとして、頭の中に様々な映像や音声が流れ込んでくる。
五感が乱れて、両目がうまく像をむすぶことができない。
「……ーい。おーい、瀬田~?」
勝田くんがやや心配そうな面持ちでこちらを伺っていた。
「ん……? あ……あぁ、ごめんごめん」
どうやら、しばらくの間フリーズしてしまっていたようだ。
僕が将棋を止めてしまったことは、友達には言っていない。新聞の将棋大会の記事に、僕の名前が一切出なくなったことに気づくほどの『僕マニア』は両親くらいなものだ。だから、勝田くんが「将棋のことなら瀬田に聞こう」と発想したことは自然だし、僕がそれを無碍にするのは彼に失礼だ。だからひとまず、今日のところは彼の相談に耳を傾けることにした。
「これは……。初形だね」
「オヤジが経営会議で新規開拓の妙案を出したらしいんだが、それに対するジジイからの返事がこの図だった……らしいんだが」
確か、勝田くんの家は総合商社で今は勝田くんの父親が社長を務めていたはずだ。しかし、初代社長であり、現会長のお爺さんが今も実質的な決定権を持っているとかいないとか。
お爺さんは度々この手の謎かけをして、周囲の人々を試しているらしい。あるいは娯楽の一種なのかもしれない。
「この図以外には文字も何もなかったそうだ。瀬田って、将棋得意だっただろ? だから、何かピンとくるものがないかなと思ってさ」
「うーん……」
正直なところ、これは将棋の実力とかそういったレベルの問題ではない気がしている。それなりに難解な局面だとか、エピソードのある有名な勝負の局面だとかならばまだ推理の取り掛かりがありそうなのだが。
(初期状態……はじまっていない、とか最初の手を動かせないとか?)
少し考えてみたが、すぐにはいい答えが出てくるような感覚がなかった。なんというか、直感的に、もっと別の解がありそうな気がするのだ。
「期限とか、そういうのは?」
「いや……。まあ、今日明日くらいに出てくればありがたいっちゃありがたいんだが。まあ、一方的な相談だし、何かひらめいたらで全然構わない」
「うーん。ちょっと考えてはみるけど……」
「悪いな。じゃあ、ちょっと俺は部活の方に行くんで。何か思いついたら、携帯のほうに連絡よろしく!」
勝田くんは白い歯をニッと出して、教室を去っていった。なんと爽やかな笑顔だろう。僕も彼のようにイケメンだったら、労せずに女の子にもてるんだろうけどなぁ。
「って、わああぁぁあ! もうこんな時間か!」
教室の壁掛け時計を見ると、既にホームルーム終了から20分が経過していた。この出遅れは痛い、痛すぎる……。
すっかり人もまばらになっている廊下を急ぎ足で駆け抜け、音楽室に近づくが
ドアには無慈悲にも「本日満員御礼 またきてね~♪」という貼り紙が貼られているではないか。
(……まあ、まだあと4日ある、し)
仮入部期間は月曜日から金曜日までの5日間ある。初日はどのみち大混雑で、諸先輩方もてんやわんやで要領が上手くつかめていないことだろう。
などと都合のいいことを頭に思い浮かべようとしたが、『隣の芝生』というか『すっぱいブドウ』というか、負け惜しみ全開なのは、自分が一番良くわかってる。
仕方ないので、他の文化部の様子でも見てまわることにした。どうせ、本入部をしてしまったら、その後は見学や体験などをする機会自体がなくなるし、話のモノダネにもなりそうだ。料理研究部とかなら、お菓子をもらえたりするかもしれない。
廊下の窓から、ふとグラウンドを見下ろすと、勝田くんがジャージ姿で準備運動をしているのが見えた。あの集団は、恐らく陸上部だろう。
(あれだけ出遅れても参加できるとは羨ましいもんだ)
陸上部は道具やスペースでそれほど制限を受けないためか、仮入部の定員オーバーというものが基本的に無いらしい。
陸上部のほかにも、サッカー部や野球部など仮入部した一年生が見渡せた。さすがに、みな地道な筋力トレーニングや声出しなどの『下積み』をさせられているが、憧れの部活に参加している、という状況に目を輝かせている。(勿論、夜のネコのような輝き方はではない)
さて、ずっと呆けているわけにはいかない。人生は短いのだ。こういう時間はもったいない。僕は廊下を歩き、順々に教室を覗いていった。書道部、演劇部、英語部……。物珍しさは感じるものの、今日一日を費やしてみようという気持ちまで起きるものはなかった。そして、とうとう教室の終端までたどり着く。
(なんだ、ここは何部だ?)
教室のドアは開け放たれているが、中からは人の気配が全くしない。恐る恐る覗いてみるが、やはり予想通り人は一人もいなかった。
(未使用の部室か……? いや、大矢高校は部室が与えられない第二部の部活も多々あるって聞いたことがあるし。たまたま留守? 便利なシモベ……じゃなくてかわいい後輩を獲得するという長重要期間の初日に?)
気になって、ついふらっと部室の中に足を踏み入れた。広さは教室の半分ほどあるものの、備品はほとんどない。部屋の中央に会議室にあるような長机とパイプ椅子が数脚配置されている。
部室の中央まで進んだところで、壁に何かが斜めに垂れ下がっているのに気づいた。
「……なんだか、今日はとってもツイてるな」
僕が目にしたのは、油性マジックで〈将棋部〉と殴り書きにされた画用紙だった。しかも、ひどい。あまりにもひどい。とても部員勧誘に力を入れているとは言い難いぞんざいな代物だ。
他の部ではとっくに活動を始めている時間なのに、入部希望の新入生おろか、先輩部員や顧問もいないこの有様。もしかしたら、やっているように見せかけてひっそりと閉店している田舎のロードサイドのラーメン屋のように、既に数年前に廃部してそのまま現在に至っている可能性もあり得る。
(まあ、そんなもんか。今どき将棋を指すヤツなんてどうかしてる)
今からめぼしい部活が見つかったとしても時間が微妙だ。かといって、部活に打ち込んでいる一年生がいる中でこのまま帰宅するのは気持ちが進まない。とりあえず、将棋部の関係者が来るまで、できるなら下校時間まではここで時間を潰させてもらうことにした。
(そうと決まったら……)
この暑い部屋をどうにかしよう。
4月上旬とはいえ、今日は日差しがとても強い。日当たりの良い部屋のようで、かつ、窓は全て閉まっているためか、室内はけっこう暑かった。窓際に歩み寄って僕は順々に窓を開けていった。クレセント錠は特に掛かっていなかったので、全ての窓をあっという間に全開にできた。
今日はそれなりに風があるようで、しばらくすると徐々に部屋の中の熱気が逃げていった。
(涼しくなったのはいいけど、風が強くて目にホコリが入りそうだな……)
グラウンド側ではなく、中庭側の部室なので砂はあまり心配なさそうだけど、強い風はあまり好ましくない。
ふと部屋の隅の方に眼をやると、金属製のロッカーが鎮座しているのに気付く。
もしやと思い扉を開くと、中には薄い盤と木の駒箱が8組ずつ並べて積まれてあった。
飴色をした木の盤を一つ抜き取って、観察してみる。決して高級なものではなさそうだが、高校の部活動の備品としてみれば十分で、かなり使い込まれていた感じを受けた。
駒箱も観察してみることにした。蓋を開けると、中身は木製の駒だった。こちらもかなり年季が入っている代物だ。
学校の部活動なら、ベニヤ板に桝目をマジックで書いた簡素な盤や、安価なプラスチック駒でも十分だと思うのだが、思った以上に備品がしっかりしたことに驚かされた。さすがそこは大矢高校というべきだろう……。
(昔は、それなりに賑わっていたんだろうな……)
手にしていた盤と駒を一組、なんとなしに長机の上に広げてみる。そして、
――ピシィッッッ
僕は、無意識のうちに駒の中から〈王将〉を選び出し、盤に打ち付けていた。
楽器とは異質の、それでいて妙に響き渡る澄んだ音。手に伝わってくる反動の感触。どれもずいぶんと久し振りのものだ。
ただ、相変わらずいい音だとは思ったものの、また将棋をしたいという気持ちは起こらなかった。
今日ここに寄ったのは、ただの気まぐれで、偶然の重なった結果にすぎないのだ。明日からは、僕は当初の予定通り、軽音楽部の仮入部員になり、音楽に高校時代を捧げることになるだろう。
などと考えていたのに、指は条件反射のように勝手に駒を摘んで初形を並べきっていた。自分の中にすっかり染み付いていた将棋に呆れを通り越して驚嘆した。
と、そのとき。教室の脇の廊下を歩く人の気配を感じた。
(もしや、関係者?)
だとしたら面倒な話だ。備品を勝手に引っ張り出したりしている以上、将棋に興味がないなどと言っても説得力がなさそうだ。
少なくとも、初形を並べられる知識はあることが明白だし、流れによってはそのまま一局……などとなりかねない。
僕の意思は実に堅く、将棋部に入る意志などこれっぽっちもないわけだが、情や賄賂でごり押しされ、仮入部させられるような事態になったら一大事だ。僕のバラ色の高校生活が一気に、退廃と虚無へと変わり果ててしまう。
「……いるの誰?」
僕に投げ掛けられた声は、大人の声でも、男の声でもなかった。それに応じる間もなく、声の主が部屋の中に入ってきた。
(……!?)
僕のボキャブラリーが貧困であるという言い訳をしつつ、一言で表すならば『美少女』というやつだった。
背丈は、男子の中では低い方の僕よりも、さらに一回り低いくらい。さらりとしたストレートの髪をポニーテールにしている。
顔立ちや容姿の整いかたは間違いなく平均以上で、テレビや雑誌に出ている芸能人が大矢高校の制服を着て目の前に現れたといわれても不思議に思わないレベルだ。
だが一点……その優位を台無しにしかねない程に愛想がなかった。特に、意図的に目を細めたり睨んだりはしていないようだが。これでは惚れるより前に逃げる男の方が多そうだ。
ただし、僕は不思議とネガティブなイメージを感じなかった。こういうとき、平均以上に色恋沙汰に縁のない僕はあたふたしたり、自ら接点を閉ざしてしまったりしてきたのだがこの瞬間は彼女の視線をしっかりと受け止めきれていた。
「将棋部の人?」
投げ掛けられた質問に、ハッとなる。想定外の出来事にすっかり〈長考〉してしまっていたようだ。
この部屋には、今は僕しかいない。当然、僕に対してされた質問だ。
「あー、えーと……?」
視線は平気だったものの、質問については参った。どう言ったものだろう。もちろん部員ではないし、仮入部員になるつもりもない、名実ともに将棋部とは全く関係のない立場だ。
しかしけれども、「ならばなんでここにいるのか」と聞かれても答えに詰まってしまう。それだけではない。質問の意図からするに、将棋部と関係がない生徒には用はないと判断されるだろう。
そして、僕の理性は彼女ともう少しだけでいいから何か話をし続けてみたいという欲求を訴えて続けている。
ぐるぐると再び〈長考〉をしている僕に、予期しない考えが頭に跳び込んできた。そして、気づいたときには僕はそれを言い終えてしまっていた。
「あ……のさ、そこの窓を閉めてったのはきみ?」
その後、訪れる静寂。僕がビシッと窓の一つを指差した直後のまま時間だけが流れていく。
「……っ」
言ってから後悔する。何で、もっと気の利いた台詞を言うことができないんだろうか……。だから『生存年数=彼女いない歴』の状態絶賛更新中なのだ。
案の定、彼女は無言でこちらの様子を伺っている。心なしか、視線も鋭さを増したように感じる。変なことをいう奴だと怪しまれただろうか。しかし、事態は思わぬ方向へ転がった。
「……何でそう考えたの? 教えて」
特段、責めるような口調ではなかった。そのことにひとまず安堵する。むしろ、僕の言葉に興味を持っているような反応にも思えた。
ただ、困ったことがある。僕自身が、何でそう考えたのか、それが分からないからだ。分からないけど、頭に跳び込んできたのだ。
昔からこういうことはよくあった。難しい問題に直面した時など、必ずではないけれど、時折妙なアイディアがふと浮かぶのだ。よく言えば、閃き、というやつかもしれない。僕はそれを勝手に〈跳躍(リープ)〉と呼んでいた。
そう正直に説明してもよかったかもしれない。しかし、運がいいことに視界の端に斜めに垂れ下がった画用紙が入ったのを機に、一気にその裏づけについての理屈が流れるように浮かんできた。
「ちょっと待って、分かったかもしれない」
「分かったかも? って、今?」
「まあまあ」
僕は〈将棋部〉と書かれた画用紙の手前まで進み、そのさらに高い部分をじっと観察する。すると、良く見るとそこにはテープの切れ端が壁に残っていた。やはり。
「多分、この画用紙は元々はあの高さに張られていたんだ。それが、一旦落ちてしまっていた。
君はそれを張りなおしたんだけど、背丈からして元の高さまでは届かないから結果的に左上だけで留めることになってしまった」
とはいえ、椅子を使って背伸びをすれば貼れない高さではない。しかし、スカート姿の女子がわざわざそんな真似はしないだろう、と心の中で補足する。
「画用紙が落ちた理由は、窓から入ってきた風の可能性が高い。元々2点で留まっていたものが1点だけに減ったわけだから、風が吹き込み続けたらまた落ちる可能性は高い。それで窓を閉めたんだ。クレセント錠まで閉めなかったのは、また戻ってくるつもりだったからか部室を開けた人が最終的に下校時間に施錠しにくると考えたから、かな?」
言い終えた自分の推測を思い返したが、矛盾やこじつけすぎた論理展開は無かったように思える。
「……」
彼女は腕を組んで少し考え混んでいる。推測が合っているかどうかは分からなかったが、僕にとってはもうどうでもよいことだ。
「まぁいいや。ところでさっきの答えは?」
「えーと、なんだっけ?」
「将棋部の人なの? 違うの?」
「うぅ……」
そういえば、元はそういう話だった。しかし、うまい理由の方は浮かびそうに無かったし、嘘で塗り固めて最後に破綻するよりはと思い、僕は高校以前の過去部分は除いて正直に話すことにした。
「――というわけで、目当ての軽音楽部が運悪く定員オーバーだったから、せっかくだと思ってぶらぶらと部活見学をしていたんだ。そうしたら、ここが空き部屋みたいになっていたから気まぐれで入って……」
「気まぐれで盤と駒を出したりするんだ?」
指差した先には、僕が並べていた駒があった。
そういえば、彼女、僕が来る前に部屋を訪れていたんだった。
「結局、部員であろうと無かろうとどっちでも構わないんだけど」
一体、何を言い出すんだろう?
いきなり「あたしと付き合ってくれない?」さすがにそれは都合よすぎの早すぎか……。そんな少年漫画のような奇跡的な展開は一切無いことをこの瀬田桂夜自身が一番自覚している。
不安半分、期待半分でドキドキしていたら。
「将棋のルールくらいは知ってるんだよね?」
(――!)
この言葉には正直不意を突かれ、そして、絶句してしまった。道を歩いていたプロ野球選手が、「バットの握り方って知ってますか?」と言われたらこんな気持ちになるのだろうか。いくら、僕が元全国3位の実力の持ち主と彼女が知らないとしても、あんまりな物言いである。僕は、どんな表情を浮かべていただろう。
結局、「あ、ああ一応は」というなんとも即妙当意でない返答を返してしまい、我ながら呆れてしまう。ここで、「こう見えても、実は元全国3位なんだけどね」とかさらっと言えていたら、「わぁ、凄いじゃん!」となって、少しお近づきになるきっかけにできたかもしれないというのに!
彼女が何を求めているかは知らないが、凡人を求めている雰囲気はない。自分の数少ないアピールポイントを活かして、この子と一気に会話をつなげられるチャンスだったかもしれないのに。
こういう積み重ねが、彼女いない歴=年齢の最大要因なんだろう、と頭の中が物凄い勢いで負のスパイラルに入りかける。
「じゃあ、あたしに将棋教えてよ」
「え!?」
「だから、しばらくあたしに色々教えて欲しいんだけど」
「え!?」
「きみ、驚くの好きだね……」
急展開、急転直下、青天の霹靂としか言いようがない。彼女がどこまでを求めているかは分からないが、数分で話尽くせるほど将棋は浅いものでもない。必然的に、しばらくは二人で話ができる時間が得られてことになるわけだ。
頭の中に、和洋折衷の様々な祝詞がこだましている。さっきまでの暗い自分よ、お帰りはそこのドアからどうぞっ。
僕の反応がなかなか帰ってこないので、彼女は立ち上がり、「イヤなら別に、他の人探すからいいよ。顧問のセンセもできるのかな……」などとてきぱきとアクションを起こそうとする。
僕は、慌てて「そんなことないよ。任せといて。昔、けっこう本格的にやってた時期もあるし」と言って、引き止める。ちゃっかりと今度はアピールすることもできた。
「そうなの? じゃ、よろしく」
そう言って、彼女は再び椅子に腰を下ろした。
*****
「さて、教えるっていっても、色々あるんだけど?」
教壇に立ち、黒板にさらさらと字を書きながら僕は背後に話しかける。
A:駒の種類、駒の動かし方。
B:ルール(成り、持ち駒、反則など)
C:手筋、戦法、囲いなど
「戦法の『戦』と『囲い』、の書き順が違うね」
(うっ……結構細かそうな子だ)
今はただ、ラポール形成に集中すべきだ。
「AからCでいうと、どこまで分かる?」
「全部知らないけど」
(……左様ですか)
「でも、Cって要するに応用テクでしょ? AとBが分かれば十分かな」
年頃の女の子が、駒の動かし方も分からない状態から、将棋を覚えたいという動機が非常に気になるが、藪蛇になっても悔やまれる。
「じゃあ、とりあえずAのところからやろうか」愚直に講座を続けることにした。










「っと、こんな感じかな。ところで……」
黒板に文字と図を書きながら、〈桂〉書いているときに、まだ互いに自己紹介をしていないことに気がついた。
「自己紹介、まだだったよね。ぼ……俺は瀬田桂夜」
さらさらと黒板の空いているスペースに漢字を書く。
「あ、ケイってそう書くんだ。なんだかミラクルだね」
ミラクルと言われ、少し救われた気がした。将棋から離れていた期間、僕は名前がイヤでイヤでしょうがなかった。
まず、名前に〈桂〉という駒の名前が含まれている。あらゆるものに名前を書く際にそれを見なければならないのは苦痛だった。
英単語の勉強をしていて、〈桂〉(K)と夜(NIGHT)で騎士(KNIGHT)じゃないか、うわ、カッコいいと思ったのはつかの間。
騎士(キシ)は棋士(キシ)と同音であることに気づき、随分と凹んだものだ。
「あたしはオリガミツキ。機織のオリ、年賀状のガ、美しい月でミツキ。苗字は濁点入っていて好きじゃないから、美月って呼んで」
「あ……えと、俺も似たような感じだから、桂夜で」
自らの歴史を振り返っても、別に苗字が嫌いだったことはない。しかし、歴史とは都合よく塗り替えられるものなのだ。気になる女の子と名前で呼び合う、これは幸福の極みとしか言いようがない。
美月は「こうした方が覚えやすいから」と言って携帯端末を構えると、黒板を撮影しようとする。僕は気を遣って黒板から離れようとしたが、
「ついでに覚えるから」と『瀬田桂夜』の隣に立たされてフレームインさせられてしまう。嬉しいような、恥ずかしいような。
「じゃあ、実際に最初の状態から動かしてみよう。勝ち負けは二の次で」
「はいよ」
美月は左の方にある角行に手を伸ばす。
(まさか!?)
そして、角行を持ち上げると、すぐ左上の歩兵の上に「ガチッ」と重ねたではないか。
初手、9七角――。
僕は思わず呼吸をするのを数秒忘れた、口をぽかんと開けたままフリーズしてしまった。
多分、将棋を指し慣れた人たちであれば、一様にみな同じ表情を浮かべるのではないだろうか。もし、将棋ファンを100人唖然とさせることができたら100万円!といった企画があれば、是非使いたいものだ。
「ねえ、今度はそっちの番でしょ。固まってないで、早くしてよ」
美月は全く自分の手に不備があるとは思っていないようだ。
「えーとさ、自分の駒の上に、自分の駒を重ねるのは無しなんだ」
僕は、初心者の心を傷つけないように言葉を選びながらそのことを伝えようとする。
「でも、さっきそんな説明してないよね?」
痛いところを突かれた。確かに、そういう説明は全く言及していなかったが。
「すまん。確かに言ってはいなかったよ。厳密に言うと、他の駒があるときは、こういう風になる。






「相手の駒はどかしてそこに行くことはできるけど、自分の駒の場合はダメってことでOK?」
「そういうこと」
「この桂馬は? 前塞がってても飛び越えられるの?」
「そうそう。香車も飛車も角も。龍や馬という駒でさえ、間に障害物があるとその先に突き進むことはできないんだけど、
桂だけはそれがないんだ。こんな風に壁があってもピョンって越えられるんだよ。
「次元を越える駒ってことね」
「えっ?」
「ほら。跳び越えられるんだから、桂だけ動きが三次元」
なるほど、言われてみれば確かに。他の駒は二次元的な動きなのに対して、桂馬の動きは特殊だ。
物心付いたときからやっていて『そういうもの』がスタートだったためか、正直「そういう考え方もあるのか」と感心してしまった。
結局、丁寧に説明を重ねたことで、この件に関してはなんとか納得してもらえたようだ。
「じゃあ……」
美月はしぶしぶ、飛車の上にある歩兵を手に取り、ひとつ前に進める。
恐らく、先ほどの件で角行が少し嫌いになったのだろう、飛車の方ををひいきにするつもりらしい。非常に動機が不純ではあるが。
(お、なかなか)
なかなか筋がいい手だ。飛車は強力な駒だ。その駒を活用する上で、〈飛車〉の前にある歩を進めていく手は非常に効率が良いのだ。
ここは褒めて伸ばしてやるところか、と思ってほめ言葉を考えていたのだが、「この桂ってやつも最初から使えないやつなのか……」などと呟いて桂馬の駒をぐりぐり押している。
(使えない……ですか)
ハハハッ。なんだか、自分を貶められているようで、僕、少しカチンときたぞ。
山あり谷ありだったが、その後は順当に進んだ。美月はなかなか学習能力が高く、『成り駒』も含めて駒の動きをあっという間に覚えてしまった。
相変わらず、表情は無愛想なままだったが、不満はないように見える。
おさらいにもう一度初形からやろうか、それともルールに移ろうかと思案していると、ドアの方に人影が見えた。
「おー!? 二人も集まったのかっ!」
入ってきたのは……1組、つまり僕のクラスの担任だった。
「あ、もしかして顧問だったんですか!?」
「いっかっにっもっ」
もしかして、と言ったのには訳がある。先生の服装だ。紺色の和服に身を包み、手許では扇子をパチパチと鳴らしている。いかにも、「将棋やろうぜ」といった風情だ。
「扇子まで持ってる。それっぽい感じ……」
女子に煽てられて気をよくしたのか、先生は「かーっかっかっ」と笑い、「常ー識だよ常識。顧問の扇子で、コモンセンス、なんてな!」などと訳の分からないことを言っている。この先生、とんだコメディアンじゃないか……。
「将棋は、お強いんですか?」
僕は思いきって尋ねてみた。繰り返しになるが、大矢高校は部活動に力を入れている。教師としての才能より、部活の顧問をこなせるかどうかが採用の決め手となる、という噂があるくらいだ。
こんなにふざけておどけていたりするが、元アマチュア名人だとか、物凄い経歴の持ち主である可能性もあるのだ。
「くく、将棋か……、やったことねぇな! より正確に言うなれば、駒を持ったことも……ねぇ!」
「はい?」
「いやあ、和服着るのが好きでさ。和風な部活の顧問になったら、放課後ずっと着ていられるだろう? 茶道部や華道部はさすがに荷が重そうだったから、将棋部を選んだわけさっ」
そうか~、なるほど~。将棋部荒廃の一端は垣間見れた気がするぞ~。
まあ、どうせ、一期一会。明日からは僕は軽音楽部に行くのだから、ここは軽く笑って聞き流すことにした。
(む。一期一会……?)
ふと考え込む。
正直、将棋部に入る気は無い。顧問の登場で、その思いはむしろ炭化ジルコニウム程度まで堅くなったと言っていい。
しかし、将棋部という接点を失うと、この美月との接点もなくなってしまうことに気づく。
(それはそれで、もったいないよな……)
ああでもない。こうでもない。将棋の次の一手を考えるように、頭の中で様々な手を読み、最良の解を探す。
(いや、部活動じゃなくても学校で会えばいいだけじゃないか。連絡先、いや、まずは何組かだけでも分かれば……)
しかし、「あ。もうこんな時間か。 あたし、ちょっと用事あるから。また明日ね」美月はカバンを肩に下げると、声を掛ける間もなく教室を出て行ってしまった。
とりあえず、明日の過ごし方については決まってしまったようだ。まあ、仮にあしたも将棋部に来たとして、仮入部期間はまだ3日ある。十分だ。
美月が出て行ったドアをボーっと眺めながら、そんなことを考えていた。すると、
「少年っ!」
「わぁ、なんです?」
突然、両肩をわっしと掴まれて僕はびくんとなる。目の前には和服姿の顧問。そして。
「汝、仮入部しちゃいなよ?」と迫ってきた。どこかの事務所社長か。
「いやです」
「なんでだよ。少年、将棋詳しそうじゃん」
黒板の文字と、僕の顔を交互に扇子で指し示しながらそう言う。将棋が詳しいことは否定しないが、それと仮入部は別問題だ。
「たまたまの、通りすがりの、事故だったんです。第一志望は軽音楽部なんで」
「なーにー? けいおんだとぅ? あんな発泡スチロールみたいなところの何が良いんだ?」
「別に、軽量とは関係ないです。あと、将棋部はいやです」
「音楽なんて、授業でもやってんだろ。あとは通学路で鼻歌でもうたってりゃ、人生の定量分に達するだろうが」
「音楽にもいろいろ種類があるんです。あと、将棋部はいやです」
「どうしてもいやか?」
「どうしてもいやです」
僕の態度が頑なと見ると、顧問は「むむむ……」と唸って考え込んでしまった。
そして、はっと何かを思いついたようで、ニヤリとしながらこう言ってきた。
「よしっ、中間テストの現代国語の点をサービスしちゃる。採点は匙加減だからなぁ。はっはっは」
「……なに、考えてるんすか! 校長に言いつけますよ!?」
一瞬、甘い誘惑に乗りそうだったが、軽音楽部への情熱と良心の呵責とで思いとどまる。
(さて、美月も帰ったし。面倒なことになる前に退散するか)
僕は、使っていた駒を手際よく元の木箱に収めて、盤と共に元あった場所に戻す。
横目でちらりと顧問を伺うと、「うああ、部員ゼロからの脱却があ……」とか「超便利なシモベができたと思ったのに……」と頭を抱えて苦悩している。
カバンを手に取り、「じゃ、俺も帰りますんで」と小声で言って教室を後にしようとするが、先に進まない。はて、と思い振り返ると、顧問がむんずと僕の制服の裾を掴んでいるではないか。
(まだ、何か取り引きを持ちかけてくるつもりなのか……?)僕が訝っていると、思わぬ方向から攻めてきた。
「……じゃあ、明日はここは閉める。備品も使わせない」
「えっ?」
予想外の攻撃。少なくとも、そんなことをされたら美月との明日の約束が果たせないことは確かだ。
(それは……やだ、けど)
というか、そもそも将棋盤と駒は学校の備品であり、顧問の権限濫用ではないか。その点を重点的にアピールするが全く取り合おうとしない。それどころか、勝機ありと見て猛攻を仕掛けてきた。
「ふっふっふっ。少年よ、あの娘に恋をしておろう? 仮入部くらい、減るもんじゃないし、むしろ、しといちゃいなよ!」
「うぐっ……」
「あの娘、かわいかったもんなー。あぁもったいないもったいない。ご縁も本日限りか……ふぅ」
「っ……」
「今日限り? やべ……。それ、顧問的にももったいなくね? お、おい、少年! どうしよう……あわわわ」
「先生がパニくってどうするんすか!」
仕方なく、僕はカバンの中からシャープペンシルを取り出し、教壇の上にあった仮入部届をさらさらと埋めていく。
「……おい、偽名じゃなかろうな?」
「さすがにひどい物言いですよ!」
ともかく、この場は仮入部でも何でもして離れるのが良策と判断した。
仮入部届を出さないと、本入部届を出すことはできない。しかし、仮入部届を出したからといって必ず本入部をしなければならないという決まりはない。
顧問の要望は「仮入部をしてほしい」で僕の要望は「とにかく、明日もこの部屋と備品を使いたい」だ。冷静に考えたところ、両者の希望は両立可能だと気づいたのだ。
僕が仮入部届を書いているのを満足そうに覗き込んでいる顧問。
「ほほう。少年の名は瀬田桂夜というのか」
僕は天を仰いだ。
「先生、担任でしょ。生徒の顔くらい覚えといてくださいよ……」
「バッキャローめ。名前なんて覚えられねーよ! 生徒から見たら担任は一人だけど、担任から見たら生徒は30人なんだ! 負け戦だろうよ。しかも、毎年毎年、慣れてきたころにシャッフルしやがって……! というか、未だに芥川龍之介と太宰治の見分けがついてない俺さまに高度なテクを要求するな!」
私立高校は個性的な教師が多いと聞いていたが、少し覚悟が足りなかったと思い知らされた。何故か自省をしていた僕に、顧問が謎の反撃をしてきた。
「お前こそ、教師に向かって呼び捨てとは聞き捨てならないぞ!」
「へ?」
「初日のホームルームの時に自己紹介しただろうが。泉西潮成と!」
(センセーショナリー? センセイシオナリ……?)
記憶の糸を手繰り寄せれば、確かに指摘された通りの映像がよみがえる。紛らわしい名前である。センセイとだけ呼ぶと、泉西なのか先生なのか特定というわけだ。
センセイセンセイと呼べば、一応は泉西先生と解釈できそうなので、これからはそのように意識することにした。
「失礼しました、泉西先生」
「ふっ、ダブル呼び捨てとは、良い度胸だなっ! これからも覚悟しておけい」
あぁ、誰か。僕を助けてください……。
*****
さすがにダブル呼び捨ての件は、泉西先生のブラックユーモアだったらしい。書き上げた仮入部届を手渡すと嬉しそうに受け取り、備品の管理場所や教室の鍵のかけ方などを非常に簡潔に説明してくれた。
そして、泉西先生は仮入部届をくるくる丸めると、舞うように、というか実際に舞いながら教室を出て行った。
(よし、あの人のことはしばらく忘れよう)
部活終了時刻まではまだ少し余裕がある。それならば、明日の計画を考えておこうと考えた。
とりあえず、明日のインフラと機会については整ったが、明後日以降はグレーと言わざるを得ない。泉西先生がいつ気まぐれを起こすか分からないから、明日中に美月とは将棋以外の接点を作るようにしたいところだ。
(携帯電話の番号とか? メールアドレスとか?)
色恋沙汰の経験が皆無の自分には、どういう話の流れで聞き出せばいいか見当もつかない。当たって砕けろ、の精神が大事なのだろうか。しかし、砕けちゃいけないだろう、という気もする。
(それにしても)
僕はふっと先ほどの出来事を思い出していた。初手9七角。歩兵の上に角行を重ねた時のことだ。
あの時はただ意表を突かれていたから、深く考えなかったが、言われてみれば角と桂は初形では全く動かせないことに気づく。
(ん?)
――かくとけいは動かせない。
――けいとかくは動かせない。
――けい、かくは動かせない。
僕の頭に〈跳躍(リープ)〉が舞い降りた。間もなく、部活終了時刻。僕は携帯端末を手に取り、勝田くんに放課後話したいことがある、とメールを送信した。
*****
「わりぃ、待たせたな!」
高校の近くにあるファミレスのドリンクバーで3種類目の炭酸ジュースであるバナナソーダを飲み始めた頃、勝田くんは現れた。
部活の後片付けをしていたのだろう。顔やジャージに少し砂ぼこりがついていた。
「で、どうだった? 解けたのか?」ストレートに聞いてくる。
自信がないわけではないが、最適解といった類のものなので「まあ、それなりに」とだけ答えておく。
僕は、もう一回例の図を携帯端末のディスプレーに表示してもらい、それを二人で覗き込むようにして話を始めた。
「まず、これは将棋の初形で間違いない。だから、最初は『始まっていない』『始めるのは待て』といったメッセージかと思ったんだ。しかし、それだと将棋以外――例えば、オセロやチェスといったゲームの図面でもよくなってしまう」
「確かにな」
「次に、各駒の状況について考えてみたんだ。新規開拓の案、つまり、最初の一手に関するものなんじゃないかなとね」
僕は、画面の角と桂を指差す。
「実は、全ての駒のうち、桂と角だけが、最初の一手では絶対に動かせないんだ。言葉遊びっぽいけど、つまり『けい、かくは動かせない』、『計画は動かせない』となるわけ」
「おおっ!? 確かに、ジジイのセンスに合ってそうな気がする! オヤジに早速連絡しよう」
その反応に、僕は自説が強化された手ごたえを感じた。
「ちょっと待って。まだ続きがあるんだ」
携帯の画面を通話モードに切り替えようと手繰り寄せようとする勝田くんを制して続ける。
「確かに『計画は動かせない』状態ではあるけど、それは条件付きなんだ。例えば、この角の右上の歩をひとつ前に進めるだけで、桂と角はすぐに動かせるようになる」
つまり、『歩を進めないかぎり計画は進められない』、逆に言えば、『勇気をもって最初の一歩を踏み出しさえすれば計画は進めていける』ということなんじゃないかな」
僕は、計画を進めるのが正解という解を提示した。相談を受けたときの感じからして、勝田くんは親父さんの案にゴーサインが出ることを望んでいるように見えたから、喜んでくれると思っていたが。
「うーむ……」
勝田くんは渋い顔で考え込んでしまった。
「まだ気がかりなことが?」
「あ~、つまりはさ、最初の方も理屈的には間違ってないわけだから、どっちも正解になりえると思えるんだよなぁ……。こっちがどっちを選んでも、ジジイが反対の方を正解だって主張しちまうと絶対に正解になれないっていうか……」
確かに。そうなのだ。その点は、僕も考えていた。しかし、僕の答えは変わらない。
「そう。この問題の答えは多分、計画を進める進めないどちらでも回答になりうると思う。
お父さんがどうしても計画を進めたい、自信があると思うなら、計画を進める方の回答、かつ、お爺さんが正解である必要があるはずだよ。
お爺さんは、どちらを選ぶかでお父さんの計画に対する自信と情熱が計れると思ったんじゃないかな」
「なるほどなぁ。とりあえず、家に帰ったらオヤジに提言してみるよ」
気づけば、自室のベッドの上に仰向けに転がっていた。
色々なことがあって、色々なことを考え続けていためだろうか。帰宅して、晩飯を食べたはずだが、良く覚えていない。
勝田くんの件もそうだけど、無事に軽音楽部に仮入部できるのかとか、将棋部(変な顧問含む)のこととか、昼間は授業もあるし、あぁ高校生ってなんて大変なんだ。
そして、
「みつき、か」
僕は呟くと、ふと気になって、普段は全く使われずうっすらとホコリをかぶっていた漢和辞典やら国語辞典やらを引っ張り出してページを手繰る。
桂という植物があることは小学生のときの課題(生い立ちの記、とかいう名前だったか)でうっすら調べたことはあったが、改めて調べてみると『月の中にあるという高い理想』を表しているらしい。
月の中といっても、月面のことだろうけれど、都合よく変換すれば、美月の中にある高い理想が桂である、ということか……。
また、月と桂が両方入る『月桂冠』は古代ギリシアで勝利と栄光のシンボルといわれているようだ。
(二人がそろえば、勝利と栄光のシンボルになるのか……)
両方とも、単なるこじつけといわれればそれまでだが、何だかとても運命的なものを勝手に感じてしまった。
とそのとき「おーい、桂夜いるか?」と僕を呼ぶ声が聞こえた。父だ。
リビングに行くと、父が夕食を食べているところだった。
「珍しく、帰るの早かったんだね」
僕は、テーブルの上に転がっている「瀬田海洋(Seta Kaiyou)」と書かれた社員証を見ながら尋ねる。
父は中小企業でシステムエンジニアとして働いている。日常的に仕事量が多く、トラブルが発生するとあっというまに終電コースで、夜に会えない日も少なくない。
「あぁ。今年は、配属したばかりの新人に『素敵な日常』を見せないように、との優しい幹部からのお達しがあったからな」
「はは……そうなんだ」
なるほど、当たり前のことだけど、4月は新たに社会人一年生になる人たちもいる。僕もあと7年くらいしたら同じ状況になるんだな。
「今年は優秀な人が入ってきてくれたの?」
「能力は問題なさそうだが、リテラシーはまだまだ教育が必要だな。パスワードをそのままディスプレイに貼り付けていたからな。それじゃあ、やりたい放題してくださいと言っているようなもんだ」
僕は少しどきりとする。僕はパスワードの類を一枚の紙にパスワード一覧としてまとめて管理していたからだ。状況は似たようなものだ。
「じゃあ、お父さんはどうしてるの?」
「簡単なものなら、〈自分なりのルール〉を心の中に決めておくのが手早いな。数字なら2つ進めるとか、英字なら1つ戻すとか、数字と英字の間にはパーセントを入れるとか。で変換する前の文字をメモしておく。これだけで随分違う」
「……なるほどね」
社会人で評価されるには、学校で教わることだけじゃダメそうだなあ。